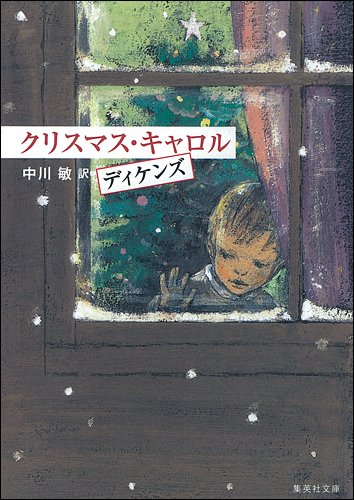hackerさん
レビュアー:
▼
誕生日がクリスマス近くだったせいで、子どものころは「クリスマスと一緒に祝いましょうね」と言われ、何の疑いもなく、それを受け入れていました。ですから、クリスマスにあまり良い思い出がないのです。
1843年刊の本書は、チャールズ・ディケンズ(1812-1870)の、おそらく最も名が知られた作品でしょう。私が最初に読んだのは、世界少年少女文学全集(という名前だったと思います)に収められていた抄訳版で、中学1年の頃だったと記憶しています。それ以来ですから、完訳版を読んだのは今回が初めてでした。
お話自体も良く知られていますが、金の亡者のような孤独な老人スクルージ、孤独であることにすら気づいていないような老人が、クリスマス・イブの夜に一人住まいの自宅で、7年前に死んだ、かっての共同経営者であるマーレイの亡霊と出会い、マーレイの亡霊が導いてきた過去・現在・未来のクリスマスの精霊たちに、自分の人生と将来の姿を見せつけられ、改心して、他者に冷酷だった生活を悔い改め、冷遇していた使用人を含め貧しき者たちに積極的に慈善行為をするようになる、というものです。
さて、この物語をどう読むかですが、訳者の中川敏は本書解説の中で、興味深い指摘を行っています。
「簡単にいえば生涯を通じて彼(ディケンズ)は人道主義者であったのには変わりない。勧善懲悪、お涙頂戴、奮闘努力の勧め、誇張した表現などの悪口はいわれてきたが、要するに読者大衆によき夢が実現する可能性だってないわけではないということをいい続けたのである。現在の時点から見ればかれの考えた社会改革も子供のための教育充実も生ぬるいものには違いない。だが、かれは政治活動家ではない。彼は作品の表現力でもって告発し、注意を喚起したのである。
ただし、彼は貧しい人の苦労を自分のことのように感じる人ではあったが、彼の立場は労働者階級とかいわゆる無産者階級の立場ではない。(中略)ディケンズは労働者階級ではなく下層中産階級の出身であり教育を受けて紳士になるのだという意識を子供のときから持っていた。(中略)1850年ごろからイギリスは繫栄と平安の時代に入るが、いっぽう拝金主義、功利主義がはばをきかせ、教会はたくさんあっても(中略)本当の信仰心はかならずしも強固とはいえない。法律、諸制度の改革も遅々たるもので、その弊害がはなはだ目立つ。そういう時代背景の中で、なるほどディケンズの倫理観は中産階級のものではあったけれども、決して上からの施しの思想で小説を書いたのではない。彼は大衆全体の向上を願っていたのだ。(中略)
最後にもう一度『クリスマス・キャロル』について蛇足を加えるなら、スクルージの改心に至る過程に文学の面白さがあるのであって、最後の大盤振舞は社会改革要求の強い表現に過ぎないのは今更いうまでもない」
さて、この文章ですが、半分賛成、半分反発というのが、私の正直な感想です。やはり、執筆当時とは時代が変わったということなのだと思います。「古い」という言葉をネガティブなニュアンスで使うのは嫌いなので、そうは言いませんが、宗教の多様性を認めるために「メリー・クリスマス」と言うのは控えようという主張(そこまでこだわらなくてもという気もしますが、もっともだとも思います)がアメリカで出る時代に、「メリー・クリスマス」とスクルージが誰にでも高らかに叫ぶエンディングには、私はもう素直に入っていけないのです。
もう一つの時代背景の変化としては、クリスマスに家族が集まってお祝いをするという習慣自体が、イギリスの一般家庭では一種の悩みの種になっていることがあります。これは経験的に知っているのですが、親とは独立して暮らすことが普通になっている昨今、毎年今年はどちらの親の家に行こうかと議論する夫婦は珍しくありませんし、姑とそりが合わないゆえに夫の実家にはいかないという女性も珍しくありません。これは、正月に家族が集まる習慣のある日本でも近年見られる傾向だと思います。一人っ子政策を取っていた中国の春節でも同じでしょう。ですから、本書で描かれている家族のクリスマスの「理想的な」過ごし方も、やはり素直に受け入れられないのです。
ただ、ディケンズの創作姿勢が、基本的には善意からのものであることは否定しません。最近、あまり聞かなくなった、ヒューマニズム若しくはヒューマニストという言葉を思い起こします。私自身もその傾向があるのは否定できないのですが、どうも途中での人間の意思や努力よりも、結果がすべてみたいな風潮が最近強いように感じる中で、そういう言葉が使われなくなってきたのは残念です。ディケンズの本質も、そこにあるのでしょうし、それは時代とは無関係なはずなのです。
お話自体も良く知られていますが、金の亡者のような孤独な老人スクルージ、孤独であることにすら気づいていないような老人が、クリスマス・イブの夜に一人住まいの自宅で、7年前に死んだ、かっての共同経営者であるマーレイの亡霊と出会い、マーレイの亡霊が導いてきた過去・現在・未来のクリスマスの精霊たちに、自分の人生と将来の姿を見せつけられ、改心して、他者に冷酷だった生活を悔い改め、冷遇していた使用人を含め貧しき者たちに積極的に慈善行為をするようになる、というものです。
さて、この物語をどう読むかですが、訳者の中川敏は本書解説の中で、興味深い指摘を行っています。
「簡単にいえば生涯を通じて彼(ディケンズ)は人道主義者であったのには変わりない。勧善懲悪、お涙頂戴、奮闘努力の勧め、誇張した表現などの悪口はいわれてきたが、要するに読者大衆によき夢が実現する可能性だってないわけではないということをいい続けたのである。現在の時点から見ればかれの考えた社会改革も子供のための教育充実も生ぬるいものには違いない。だが、かれは政治活動家ではない。彼は作品の表現力でもって告発し、注意を喚起したのである。
ただし、彼は貧しい人の苦労を自分のことのように感じる人ではあったが、彼の立場は労働者階級とかいわゆる無産者階級の立場ではない。(中略)ディケンズは労働者階級ではなく下層中産階級の出身であり教育を受けて紳士になるのだという意識を子供のときから持っていた。(中略)1850年ごろからイギリスは繫栄と平安の時代に入るが、いっぽう拝金主義、功利主義がはばをきかせ、教会はたくさんあっても(中略)本当の信仰心はかならずしも強固とはいえない。法律、諸制度の改革も遅々たるもので、その弊害がはなはだ目立つ。そういう時代背景の中で、なるほどディケンズの倫理観は中産階級のものではあったけれども、決して上からの施しの思想で小説を書いたのではない。彼は大衆全体の向上を願っていたのだ。(中略)
最後にもう一度『クリスマス・キャロル』について蛇足を加えるなら、スクルージの改心に至る過程に文学の面白さがあるのであって、最後の大盤振舞は社会改革要求の強い表現に過ぎないのは今更いうまでもない」
さて、この文章ですが、半分賛成、半分反発というのが、私の正直な感想です。やはり、執筆当時とは時代が変わったということなのだと思います。「古い」という言葉をネガティブなニュアンスで使うのは嫌いなので、そうは言いませんが、宗教の多様性を認めるために「メリー・クリスマス」と言うのは控えようという主張(そこまでこだわらなくてもという気もしますが、もっともだとも思います)がアメリカで出る時代に、「メリー・クリスマス」とスクルージが誰にでも高らかに叫ぶエンディングには、私はもう素直に入っていけないのです。
もう一つの時代背景の変化としては、クリスマスに家族が集まってお祝いをするという習慣自体が、イギリスの一般家庭では一種の悩みの種になっていることがあります。これは経験的に知っているのですが、親とは独立して暮らすことが普通になっている昨今、毎年今年はどちらの親の家に行こうかと議論する夫婦は珍しくありませんし、姑とそりが合わないゆえに夫の実家にはいかないという女性も珍しくありません。これは、正月に家族が集まる習慣のある日本でも近年見られる傾向だと思います。一人っ子政策を取っていた中国の春節でも同じでしょう。ですから、本書で描かれている家族のクリスマスの「理想的な」過ごし方も、やはり素直に受け入れられないのです。
ただ、ディケンズの創作姿勢が、基本的には善意からのものであることは否定しません。最近、あまり聞かなくなった、ヒューマニズム若しくはヒューマニストという言葉を思い起こします。私自身もその傾向があるのは否定できないのですが、どうも途中での人間の意思や努力よりも、結果がすべてみたいな風潮が最近強いように感じる中で、そういう言葉が使われなくなってきたのは残念です。ディケンズの本質も、そこにあるのでしょうし、それは時代とは無関係なはずなのです。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:集英社
- ページ数:228
- ISBN:9784087520170
- 発売日:1991年11月20日
- 価格:500円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。