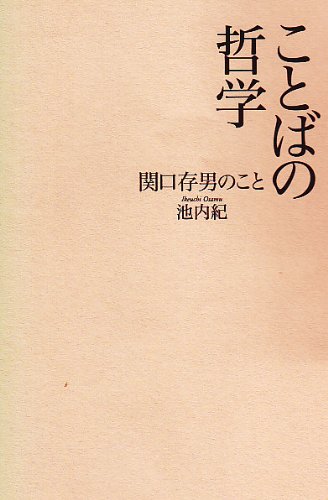有坂汀さん
レビュアー:
▼
本書はドイツ文学者、エッセイストである池内紀先生によるドイツ語学者、関口存男先生の伝記です。ドイツ語に取りつかれた関口先生の色濃い「ことばの哲学」を追求する一冊で、求道的な生き様が心を打ちます。
関口存男。
僕が関口先生のお名前を知るきっかけになったのは哲学者、國分功一郎先生の人生相談『哲学の先生と人生の話をしよう』(朝日新聞出版)を読んだことであり、語学に悩む相談者に関口先生のありがたいお言葉を引き合いに出したキレッキレの回答をし、さらに参考文献として本書を上げていたからです。
なお、ツイッター上には関口先生の珠玉の名言をつぶやく関口存男bot(@sondern_bot)があり、興味を持ったか方は是非フォローいただき、関口先生のお言葉
「…純眞とは云いながら、まだ本當に純眞なのではなくて、馬鹿だから純眞なんだ…」
「要するに、つまり、「量は質を変える」ということ―というよりもむしろ、量は「ある種の大量に達すると」質を変える、ということを言っているのです。」
「寸暇を利用して毎日缺かさずやる方が、尺暇、丈暇を利用して時々ほつたらかしてしまう行き方よりは、長い間には遥か遠い所へ達します。居眠りする兎よりは、居眠りしない龜の方がスピードが出るのです。」
に背筋を正される。あるいは魂が震えるような経験をしてただけると幸いです。
さて、話を本題に戻すと、本書は関口先生の生涯をまとめた伝記であり、関口先生がその生涯をかけてまとめたドイツ語文法。そのルーツはドストエフスキーの『罪と罰』のドイツ語版であり、関口先生はひたすら読みふけることによって基礎を身に着け、さらにそこからフランス語、ラテン語、ギリシャ語、英語、その他の言語も、それぞれの語学を扱う専門学者と同等、あるいはそれ以上のレベルまで習得したというのですから、圧巻の一言に尽きます。
しかし、関口先生の人生は波乱万丈そのものであり、陸軍士官を挫折したり、戦時中は他のドイツ文学者たちが、『日独伊三国同盟』という世相のもとに時局に便乗し、ナチスの「意向」に沿った文章を訳すのに対し、関口先生はそれを拒否したがゆえに不遇をかこったり、戦後は手のひらを返すように彼らがその事実から目をそむけ、トーマス・マンなどを紹介して戦後民主主義を謳歌する一方で、関口先生は経歴上の問題で公職追放の憂き目に遭い、ついに大学教授の職に復帰することなく、予備校の先生として糊口をしのぐほかは「畢生の仕事」であるドイツ語文法の研究に自らの情熱を注ぎこむ…。
その壮絶、かつ求道的な生き方は単純にすごすぎて言葉も出ないほどでしたが、関口先生のおっしゃる
「世間が面白くない時は勉强に限る。失業の救濟はどうするか知らないが個人の救濟は勉强だ。」
の言葉の裏にはこういうものがあったのかと、深い感動を覚えました。
一つの道にすべてを賭けることの苦悩と歓喜が、この1冊に記されております。
僕が関口先生のお名前を知るきっかけになったのは哲学者、國分功一郎先生の人生相談『哲学の先生と人生の話をしよう』(朝日新聞出版)を読んだことであり、語学に悩む相談者に関口先生のありがたいお言葉を引き合いに出したキレッキレの回答をし、さらに参考文献として本書を上げていたからです。
なお、ツイッター上には関口先生の珠玉の名言をつぶやく関口存男bot(@sondern_bot)があり、興味を持ったか方は是非フォローいただき、関口先生のお言葉
「…純眞とは云いながら、まだ本當に純眞なのではなくて、馬鹿だから純眞なんだ…」
「要するに、つまり、「量は質を変える」ということ―というよりもむしろ、量は「ある種の大量に達すると」質を変える、ということを言っているのです。」
「寸暇を利用して毎日缺かさずやる方が、尺暇、丈暇を利用して時々ほつたらかしてしまう行き方よりは、長い間には遥か遠い所へ達します。居眠りする兎よりは、居眠りしない龜の方がスピードが出るのです。」
に背筋を正される。あるいは魂が震えるような経験をしてただけると幸いです。
さて、話を本題に戻すと、本書は関口先生の生涯をまとめた伝記であり、関口先生がその生涯をかけてまとめたドイツ語文法。そのルーツはドストエフスキーの『罪と罰』のドイツ語版であり、関口先生はひたすら読みふけることによって基礎を身に着け、さらにそこからフランス語、ラテン語、ギリシャ語、英語、その他の言語も、それぞれの語学を扱う専門学者と同等、あるいはそれ以上のレベルまで習得したというのですから、圧巻の一言に尽きます。
しかし、関口先生の人生は波乱万丈そのものであり、陸軍士官を挫折したり、戦時中は他のドイツ文学者たちが、『日独伊三国同盟』という世相のもとに時局に便乗し、ナチスの「意向」に沿った文章を訳すのに対し、関口先生はそれを拒否したがゆえに不遇をかこったり、戦後は手のひらを返すように彼らがその事実から目をそむけ、トーマス・マンなどを紹介して戦後民主主義を謳歌する一方で、関口先生は経歴上の問題で公職追放の憂き目に遭い、ついに大学教授の職に復帰することなく、予備校の先生として糊口をしのぐほかは「畢生の仕事」であるドイツ語文法の研究に自らの情熱を注ぎこむ…。
その壮絶、かつ求道的な生き方は単純にすごすぎて言葉も出ないほどでしたが、関口先生のおっしゃる
「世間が面白くない時は勉强に限る。失業の救濟はどうするか知らないが個人の救濟は勉强だ。」
の言葉の裏にはこういうものがあったのかと、深い感動を覚えました。
一つの道にすべてを賭けることの苦悩と歓喜が、この1冊に記されております。
投票する
投票するには、ログインしてください。
有坂汀です。偶然立ち寄ったので始めてみることにしました。ここでは私が現在メインで運営しているブログ『誇りを失った豚は、喰われるしかない。』であげた書評をさらにアレンジしてアップしております。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:青土社
- ページ数:225
- ISBN:9784791765744
- 発売日:2010年10月21日
- 価格:1890円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。