暴れん坊本屋さん (1)





わかりたい、あなたのための、出版業界入門
数年前、『誰が本を殺すのか?』が話題となった。出版業界の内情に多少とも関心のある者にとっては、さほ…

本が好き! 1級
書評数:692 件
得票数:8228 票
学生時代は書評誌に関わってました。今世紀に入り、当初はBK1(現在honto)、その後、TRCブックポータルでレビューを掲載してました。同サイト閉鎖から、こちらに投稿するようになりました。
ニックネームは書評用のものでずっと使ってます。
サイトの高・多機能ぶりに対応できておらず、書き・読み程度ですが、私の文章がきっかけとなって、本そのものを手にとってもらえれば、うれしいという気持ちは変わりません。 特定分野に偏らないよう、できるだけ多様な書を少しずつでも紹介していければと考えています。
プロフィール画像は大昔にバイト先で書いてもらったものです。





わかりたい、あなたのための、出版業界入門
数年前、『誰が本を殺すのか?』が話題となった。出版業界の内情に多少とも関心のある者にとっては、さほ…





「世界は本屋の中にある。」(「はじめに」の書き出し、3頁)
日本語のタイトルからは、著者の好みに応じた本屋さん探訪記がイメージされますが、主軸をなすのは、本書…






風を描く作家....
ちょうど先日、都内で開催されていた小松崎茂氏の回顧展に行った。元プラモデル少年として喜んで出かけた…






「かつてのプロムナードに高速道路を通してしまったため、風致景観が著しく損なわれた。これは震災復興の遺産を食い潰しているという東京都市計画の貧困を象徴している。」(「隅田公園」のキャプション、13頁)
東京の都市論もしくは都市計画の歴史についての本を読んでいると、かなりの頻度で言及されかつ理想視され…






ファンタジーなきファンタジー、ミステリーなきミステリーという力技
タイトルからすると、一見、ファンタジー。そして著者の名をみれば、中学校を舞台にした爽やか系青春ミス…






「揃っていません、角田先生・・・。一人、欠けています」(ある年の卒業式にて、255頁)
実に重たいテーマを扱っているにもかかわらず、なんと清々しい読後感であろうか、とついため息をついてし…






元祖ロストジェネレーションの「人生いろいろ」
ロストジェネレーションということばが、現代日本に広がって久しい。バブル崩壊以後の経済不況を背景に、…





「そこで、わたしたちは『事によるとおもしろいことになるかもしれない、ともかくいってみよう』といわき市にいくことにしました。」(プロローグ 一通の手紙、13頁)
フタバスズキリュウ。ある世代以上の人達にとっては、懐かしくも身近な「恐竜」の名前である。日本では恐…






「それがどう云ふものか話を作ることに興味を失つて、変な云ひ方だが、作らないことに興味を持つやうになつた。自分を取巻く身近な何でもない生活に、眼を向けるようになつた」(307頁)
本書の刊行は2018年、「今なお新刊が編集されるのか」と驚きをもって手にした1冊です。5つの中短編…






「アジェは最高の名人芸の極点に到達していた。だが、ずっと日の当たらない場所で生きてきた偉大な達人につきものの頑固な謙虚さで、到達した印の旗をそこに立てなかった。」(写真小史、34ー35頁)
『複製技術時代の芸術』などで知られる、著名な思想家による写真論である。「写真小史」を含め、個別の写…





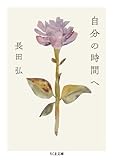
「自分の時間は、自分だけでゆたかにすることはできない。」(あとがき、188頁)
店頭での名作エッセイ集とかいう売り文句に釣られて購入したものです。著者は「深呼吸の必要」などで有名…






彼もまた、大恐慌の子どもだった。
『仕事!』をはじめ、米国におけるオーラルヒストリーの第一人者として知られる著者自身のヒストリーである…






「文化が、外側から、もしくは上から与えられるものでなく、一人一人の内側から、内発的に創造されるものであるとするならば、都市もそのようにつくられてきたに違いない」(9頁、本書冒頭)
明治前半期に日本で盛んにつくられた和洋折衷建築(擬洋風建築)を、日本の建築、否、日本近代史もしくは…






「満里亜という女の目は、どうして暗いところでもあんなに明るんで見えるのだろう。」(1章の冒頭、24頁)
「この作家に、このような長篇作品をあったっけ?」と手にとってみた作品です。 それもそのはず、単…






「五年半、夫と暮らしたミラノの家のそばの電車道には、35番の市電が通っていた。」(「電車道」の冒頭、34頁)
1990年代の読書シーンに登場し、圧倒的な賞賛をもって迎えられたのが須賀敦子さんです。注目を集めた…






「どうか今の記憶が いつまでも なくなりませんように」(6巻、129頁)
やはり金目綿花奈さんの「その後」が気になってしまい、秋から冬へという季節が描かれる5・6巻を手にと…






「そう、あのレコードの中の曲は、すべてこの町の日常から生まれたものです。ファンタジーというのは、じつは日常を知らないと生まれないものだと、あとになって気付きましたよ。」(フィル・ブラウン、108頁)
「ミリルトン探偵局シリーズ」という名で刊行された2冊です。この探偵局は、語り手の「おん」と小説家の…






「一部の大学の研究者を除いて林芙美子を論じる人は少ない。生前人気のあった作家ほど亡くなると忘れられるのが早い。私自身も長いこと『林芙美子なんか』と思っていた。『通俗』と軽んじていた。」(393頁)
著者の川本三郎氏には本作の前に『荷風と東京』という著作を出しており、出版社は違えど造本の雰囲気から…





「本書の主なテーマは、美しく魅力的な純粋数学と複雑な実生活上の問題に適用するために必要な統計手法との衝突である。」(日本語版への序文、iii)
「データサイエンス」が時代の流行語になり、また学部学科名に冠せられるようにもなった。その重要な部分…






「君らが充実させたいと願っている君らの人生。その中に真実はないぞ、と。(中略)人生の中に真実はないのさ。/はっきり言おう。/真実があるのは虚構の中だけだ。」(武井京太郎、511頁)
クルーズ船を舞台にしたミステリーと書くと、なんとも旅情をかきたてる感じがしますが、舞台設定はかなり…