日本とドイツ ふたつの「戦後」





二つの国は、1945年に敗戦国になり、そこから復興の道を別々に辿ります。その共通点と相違点はどこにあるのか。そして、現在はどうか。在独25年になる筆者が浮き彫りにします。
「2008年3月18日、ドイツ連邦政府のアンゲラ・メルケル首相は、エルサレムのイスラエル議会で約24…

本が好き! 1級
書評数:778 件
得票数:15468 票
後期高齢者の立場から読んだ本を取り上げます。主な興味は、保健・医療・介護の分野ですが、他の分野も少しは読みます。でも、寄る年波には勝てず、スローペースです。画像は、誕生月の花「紫陽花」で、「七変化」ともいいます。ようやく、700冊を達成しました。





二つの国は、1945年に敗戦国になり、そこから復興の道を別々に辿ります。その共通点と相違点はどこにあるのか。そして、現在はどうか。在独25年になる筆者が浮き彫りにします。
「2008年3月18日、ドイツ連邦政府のアンゲラ・メルケル首相は、エルサレムのイスラエル議会で約24…





親鸞を開祖とする、日本最大の仏教宗派である、浄土真宗の実態を、歴史的に位置付けて明らかにしようとした、意欲的な本です。親鸞の生涯と信仰、その継承者たちの苦悩と教団の発展などについて鋭く考察しています。
家の宗教が、浄土真宗であることから、日常的にその影響を受けて育った私には、この宗教が広く流布している…





「ものと人間の文化史」シリーズの一冊で、「歯・口」と「歯科医学・医療」の歴史について、一般の人にも興味を持てる内容が盛り込まれています。「物」を集めるばかりでなく、系統的に纏められた労作です。
『歯』という題ですが、歯そのものについて書いたものではなく、歯に纏わる様々な「もの」について書かれた…





戦前、満州で活躍をした政治家、岸信介は、首相となり、日米安保条約の改定を行い、日本中が大荒れしました。岸の孫、安倍晋三は「日本を取り戻す!」と絶叫しましたが、これは議論のポイントを間違っているのです。
「満州国」は1932年3月1日に成立し、1945年8月17日に崩壊した立って13年少しの短い期間、存…




「嫌日国」については、種々出されていますが、「親日国」については、恥ずかしながら、あまり見たことがありません。この本では、なんと63カ国について、それぞれの度合いに応じて親日国ぶりが示されています。
年末年始には、肩の凝らない、軽い話題の本を、と思って手にしましたが、一つ一つの国については、2ページ…




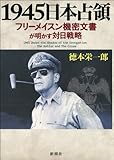
GHQ最高司令官だった、ダグラス・マッカーサーは、フリーメイスンの最高幹部であったことから、日本に対する占領政策の基本哲学を探っています。
〈フリーメイスンとは中世英国の石工組合を起源とする世界的組織である。宗教組織ではないが会員は「至高の…





夏の終わりに手配をしていた旅行が、迷走台風のせいで、延期のやむなきにいたり、九月初めに、当初計画していた「信州・安曇野」に行くことになり、その「安曇野」について書いた本をやっと見つけて読んでみました。
信州・長野県の観光案内書ならば「軽井沢」や「上高地」、登山案内ならば「北アルプス(飛騨山脈)」「南ア…





前著『昭和史講義』に続く第2弾です。ここでも、わが国の戦争への道筋を辿っています。時代の流れ、政治家の資質そして国際環境の絡み合い、そして、国民の生活がどのように変わっていったかを明らかにしています。
前著に引き続き、最近の研究により、昭和戦前期の日本が、破滅の道をひた走った原因を究明しています。歴史…






なぜ昭和に日本が戦争へと向かったのか。その失敗の原因はどこにあったのか。その解明に向けて、16人の気鋭の研究者たちの最新成果を結集し、昭和史の真実を探り、最良の戦前期昭和史のテキストを目指しています。
昭和初期の外務大臣をつとめたのは、幣原喜重郎(1924~27年、29~31年)であり、その幣原は、敗…





ノンフィクション作家として、昭和史についての本が数多くある著者が、昭和の大事件を七つ選び、激動の時代を振り返っています。
この本で取り上げている七大事件とは、新しい順に並べると次の通りです。 ①ロッキード事件(昭和…





明治以降のわが国の発展は、江戸時代の科学技術力が、基礎となっているとして『天地明察』の著者と、科学技術史家・鈴木一義の対談を始め、天文暦学、測量術、医学、数学・和算、江戸理系人の列伝が書かれています。
口絵「江戸時代、こんなものが生まれていた!」には、次のようなものの写真が掲げられています。 …





彦根藩井伊家の世田谷領の代官・大場与一と妻・美佐が夫婦ともども書き残した幕末から明治にかけての日記をもとに、歴史上無名の人々の視点から見た、もう一つの幕末維新史です。
かの『武士の家計簿』(磯田道史著)以来、江戸時代の原典物が多く出されていますが、この本もその一つです…





岩波新書の「シリーズ日本近代史④」として出されている本です。ここで取り上げられているのは、巨大城下町・江戸です。そして「社会=空間構造論」「身分的周縁論」「文節構造論」の三つの方法を駆使しています。
第一章では、城下町という都市の性格を考えながら、その最大規模のものである江戸がどのように形成され、巨…





『昭和史』に続き『幕末史』を著した著者が、その「幕末」に日本のすべてが変わったとの認識のもとに「今」だからこそ、振り返る意味があるとして、その裏面史を描いた、警世の書です。今年の菊池寛賞受賞者です!!
200年以上続いた鎖国が、徳川幕府とともに崩れた理由として、著者が挙げているのは、幕府の財政が破綻し…





災害王国日本の歴史を、災害の復興という視点から書かれた本です。古代、中世、近世、明治以降の濃尾地震、三陸地震津波、関東大震災、さらに阪神・淡路大震災を取り上げ、災害から立ち上がる人々を描いています。
本書の巻末に、災害一覧が年表になって示されています。その中で、江戸時代以降の地震・津波の項を抜き書き…






マルクス(主義ではない)歴史学者と自認している著者が、日本の歴史学史をまとめた大冊です。明治以来の日本の歴史学のあり方についての認識と、それと不可分の歴史教育のあり方を、批判的に述べています。
著者は、一橋大学名誉教授であり、この本は死去の約一年前に発行された、多分最後の著作であろうと思われま…





お札に描かれた人物や、東京都内に現存している銅像の主から、我が国の近代明治期と、それを生み出した近世江戸期との関連を見ることで、歴史学誕生のルーツを探り、近代国家における「歴史学」の在り方を語ります。
現在の紙幣に描かれている人物は、福沢諭吉、樋口一葉、野口英世であり、少し前には、新渡戸稲造、夏目漱石…





伊勢神宮と出雲大社。この二つの神社は、明治以降その位置が大きく変動し、現在もなお続いてます。それは何故なのか? また、著者の個人的経験として「さいたま市」の成立までの経緯を書いています。
〈出雲〉とは、島根県東部の旧国名というよりは、むしろ出雲大社、もしくはそこに祀られたスサノヲノミコト…





2010年3月に第1刷。CBSのスポーツアナウンサーであった著者が、1992年の初夏に訪れたカナダ・バンクーバーで偶然出会った日系人から聞いた、戦前に誕生した野球チーム「バンクーバー朝日」の物語です。
バンクーバー朝日は、移民排斥の只中にあった、1914年にバンクーバーの日系カナダ人社会の中に誕生した…





1959年12月16日、最高裁の「(安保条約のような)我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有する問題については、憲法判断をしない」との判決により、法治国家崩壊の状況になっています。
1959年3月30日の「砂川事件」に関して東京地裁で言い渡された、「米軍の日本駐留は憲法第九条に違反…