フェイクニュースを哲学する──何を信じるべきか





情報氾濫時代の、専門家の発言、ネット記事から陰謀論まで、情報を吟味するとはどういうことなのか、を論じた哲学的実践の書と、筆者は述べています。この時代に生きている者にとって、参考になります。
この本では、次のようなことを問題として取り上げています。 1.「フェイクニュース」という現象に…

本が好き! 1級
書評数:780 件
得票数:15504 票
後期高齢者の立場から読んだ本を取り上げます。主な興味は、保健・医療・介護の分野ですが、他の分野も少しは読みます。でも、寄る年波には勝てず、スローペースです。画像は、誕生月の花「紫陽花」で、「七変化」ともいいます。ようやく、700冊を達成しました。





情報氾濫時代の、専門家の発言、ネット記事から陰謀論まで、情報を吟味するとはどういうことなのか、を論じた哲学的実践の書と、筆者は述べています。この時代に生きている者にとって、参考になります。
この本では、次のようなことを問題として取り上げています。 1.「フェイクニュース」という現象に…
![]()





森崎和江は、1927年に朝鮮で生まれ、2022年に95歳で死去するまで、たった一人、徒手空拳で男と女の断層を乗り越える道を追求していこうとした。
森崎和江は、当時は植民地であった朝鮮で生まれ、日本という国と自分自身の原罪を生涯にわたって見つめ続け…



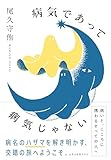
精神科医で詩人という筆者の論点は、人が人を「病気」という視点を用いてジャッジすることの倫理性であり、医師という職業に対する社会のレフェリーが、最近どんどん厳しくなっている現実の姿であることのようです。
この本が取り上げている病気とは、次のようなものです。 1-1 受診し診断された、検査で異常があ…




近年の日本の博士号取得者のうち、アカデミア(大学などの公的な研究環境)を離れて、民間企業、非営利団体、個人事業主、その他に従事している者は、3割強との事ですが、そういった人たちの言葉をまとめた本です。
この本に取り上げている人は、21人で、その職種は多岐にわたっています。その内容は、次の通りです。 …





制度が開始されてから、四半世紀を経た、介護保険の実態と課題を、余すところなく解説し、誰もが安心できる介護生活を送るための決め手を探った本、と筆者は書いていますが、これから、本当に大丈夫なのでしょうか?
筆者が、介護の現場として掲げているのは、①介護現場(在宅・施設における介護の現場)、②政策決定過程の…





現在のイスラエルは、1948年5月14日に独立宣言が発せられ、アメリカやソ連は直ちに承認しましたが、アラブ連盟5カ国からは宣戦布告と攻撃が始まりました。それから、75年経った今も、戦いは続いています。
イスラエルがどんな国かを、多くの地図と図表で可視化している本書は「歴史地理学」の優れたテキストである…




政治の腐敗や堕落を止める「自浄能力」が働かなくなくなり、倫理の底が抜けてしまった日本社会/先進国から野蛮な国へと転落した。と表紙カバー裏に記している本書には、今の日本に見られる不正や腐敗を暴いています
この本で、筆者が訴えていることは、次の通りです。〈 〉内には、その主な項目の流れを挙げました。 …





憲法学者であり、刑事告発など市民運動家である筆者が、これまでの活動の成果を総合的にまとめた本だそうです。
この本の内容は、次の通りです。 プロローグ 第1章 政治家の収入源はどうなっているのか…
![]()





「保護司」は、非常勤の国家公務員であり、他の職業を持ちながら、ボランティアとして、安心な地域社会づくりに貢献している人たちです。その数は、全国で四万七千人ほどで、その平均年齢は、65.6歳だそうです。
「保護司」が担っている仕事は、犯罪や非行をした人の立ち直りを助け、その再犯を防ぎ、新たな被害者を生ま…





身体や健康に関する本かと思いきや、SDGsをウンコから考え、「学校のトイレ」から世界のトイレ事情を取り上げ、「生きていることは、常にウンコとともにあることを考える」という視点で書かれた本でした。
世の中には、「汚い」と「きれい」では割り切れない、清濁入り混じった混沌とした事柄があり、その中に身を…




![週刊金曜日 2024年11/29号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51NHPKukPQL._SL160_.jpg)
特集「俳句界の巨魁 高濱虚子 生誕150年」が出ていたので、読んでみました。時事問題週刊誌としては、珍しい企画です。
全66頁の中で、表紙を含め、15頁を占めている特集号です。 特集の目次は、次の通りです。( )…




1932年から、45年までのわずか13年間、現在の中国東北部に存在した「偽満州国」とは、どんな国であったのか。その実像を、多数の写真と記述によって振り返っている本です。
「満州国」は、その淵源は1904年の「日露戦争」にあり、満州事変(1931年)を経て、1032年に建…




JR中央線は、東京から高尾の路線ですが、この本で取り上げているのは、立川・日野、国立、国分寺、小金井に多摩霊園を加えた物語です。いささか地域的に偏っていますが、筆者の思い入れを綴った本になっています。
「誰もが知る人の、誰も知らない」エピソードを数多く載録できた、と筆者は自負しているようですが、この本…





「日露戦争」について書いている本は、沢山ありますが、「日ソ戦争」について書いた本は。これまで殆どなかったことは、いささか関わりのある者として、驚くとともに、ようやく世に出たことに感謝したいと思います。
日露戦争が終わってから、四十年後に「日ソ戦争」が起きました。戦争をした期間は、1か月ほどですが、両軍…




「祭りという非日常に身を侵すことによって、心と身体は少しだけ軽くなる。」という筆者が、全国の18の祭りの現場に出かけて、「まだまだこの世は捨てたもんじゃない」というかすかな希望を抱いて綴った本です。
この本で取り上げているのは、次の18地域でなされている、お祭りです。 1.ナマハゲ(秋田県男鹿…





コロナ禍の際に、感染症対策の専門家として時の政府の方向性とは真っ向から反するような発言をした、尾身茂は「ルビコン川を渡った」と語った。これに政治はどのように対応したのかを検証した本のようです。
この本の語り手は、尾身茂であり、聞き手は、東大教授で行政学・政治史・オーラルヒストリーを専門とする、…





日本列島の成り立ちとかたちを概観し、この列島で生活していくためにぜひとも押さえておきたい資源――水、塩、燃料にはじまり、鉄や黄金などの「贅沢品」まで――暮らす上での不可欠な財産目録を示している本です。
高校の社会科で「人文地理」を選択したのが始まりで、「地理」には関心を持ってきましたが、「自然地理」や…




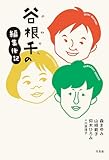
「谷根千」とは、『谷中・根岸・千駄木』の略称で、25年間にわたり発行され、2009年に通巻94号で終刊した、伝説の地域雑誌の編集後記と、対談「媒体づくりは楽し」を収録したユニークな本です。
江戸の面影を残す寺町■谷中 かつては遊郭も栄えた職人の町■根津 鴎外、漱石ゆかりの■千駄木山 …
![]()




「経営の神様」とか、「日本一のお金持ち」とか言われた、松下電器の創業者である松下幸之助の伝記です。1989年に94歳で死去後、35年経って出版された本書は、まるで、モノトーンのパッチワークのようです。
松下幸之助について書かれた本はたくさんあり、また、残した言葉もたくさんありますが、その言葉を本当の意…





約80年前の記憶を記録した本です。この本が取り上げているのは、たった10編ですが、その背後には、何万といわれている体験が重なり合って、見えてきます。
この本は、「読売新聞」に2023年8月から連載された「引き揚げを語る 戦後七八年」 に掲載された記事…