文盲 アゴタ・クリストフ自伝

亡命で辿りついた国の言語は、読み書きができず、突然文盲と同じ、世界で生きることを余儀なくされるアゴタ。孤独の中で、静かに戦いながら生きる。母語が人間形成に深く関わっていることを鋭く洞察している。
この自伝は百頁にも満たない小さなものだ。そして、静かに語られている。 しかし、深い洞察が書かれ…

本が好き! 1級
書評数:127 件
得票数:734 票
偶然迷い込んだ「本が好き!」サイト。
ますます、本が好きになりました。
旅と共に読書も私を知らない世界に誘ってくれるので、その恩恵にどっぷり浸り、心豊かに過ごしたいです。

亡命で辿りついた国の言語は、読み書きができず、突然文盲と同じ、世界で生きることを余儀なくされるアゴタ。孤独の中で、静かに戦いながら生きる。母語が人間形成に深く関わっていることを鋭く洞察している。
この自伝は百頁にも満たない小さなものだ。そして、静かに語られている。 しかし、深い洞察が書かれ…

お正月に百人一首をどのくらいの人がするのでしょうか。読み方がわからないと投げてしまう前に一度この本を手にとって見ることをおすすめします。親切丁寧な解説で、わかり易く、光琳カルタをみるだけでも楽しい。
この冬は、格別寒く、今日、梅の花を今年初めて見ました。 人はいさ心も知らずふるさとは 花ぞ…
![]()
バリで見た影絵のラーマヤナが、どんな話か知りたいと思っていました。マハトマ ガンジーはラーマヤナを読む事を日課にしていたという。古代インドの叙事詩の魅力は。ガンジーは何を思い読み続けたのか。その理由は。
コーサラ国の王子ラーマが理不尽な森流しの刑を受け入れ、苦難を共にしているシーター妃は羅刹王ラーヴァナ…

ファインマンさんの好奇心旺盛で、物怖じせず、素直な生き方はとても魅力的です。
この本には、いたずら好きのファインマンさんの面白おかしい話の中にさらっと「とても大切なこと」が沢山詰…

短歌の世界の深さと豊かさに触れた。歌を詠むことは、自分の感情に流されるのではなく、一度客観視し、更に深めて行くことなのだろうか。それを互いに読み合うというのは、自分を晒し自分の人生を抉る 作業なのか。
表紙も挿絵も併せて、ひとつの「本」を形成していると思う。 そこで、まずは、表紙の茄子の絵につ…
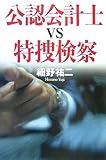
これは中世の魔女裁判なのか。それとも独裁国家での話なのか。不条理の世界に突然放り込まれた公認会計士が逮捕から、控訴棄却までの経緯についての詳細を明らかにすることにより、特捜検察についての問題点を糾す。
これは一体いつの時代のどこの話なのか。まるで、不条理劇を見ているような、無力感に襲われる。 これは…

犬と一緒に暮すことにより、得られた様々な感覚は人生に彩りを添え、豊かにした。ハラスの生涯は大きな喜びと深い悲しみを与えた。辛さが身にしみても、一緒に過ごした日々の豊かさを考えれば、余りあるものがある。
ハラスと暮らすうちに様々な発見をし、翻って、人間の有り様を見つめ直す。この本を読んでいると、 著者…





自分のための人生を生きていると言えるのだろうか。自分のための人生を生きるとはどういうことなのか。人は一人では生きられない。自分のための人生を生きるためにはどのように折り合いをつけたら良いのか。
訳・解説 渡部昇一「自分で、自分の人生を選択し、自分の今を大切にしてきた人生を背景にもつと、必ずそ…

美に関する膨大な知識を集めたとしても、初めて提示されたものが美しいのかどうかを測ることはできない。「だからこそ、たんびたんびに『美しい』と思って発見してしまう能力が大切なのだ、と考えているのです。」
橋本治氏の「人はなぜ『美しいが』わかるのか」についてを文章にするという試みは 果たして成功している…

斎藤茂太氏のユーモアに溢れた語り口そのままで、楽しく読みながら、ふと心にしみる。秋も深まったこの時期にカバンに詰めておけば、どこでも開いて、ホッコリ温かい気持ちになれます。
「いつも私は、『言葉の力」を味方にしてきた」と副題にあるとおり、いい人生を作るためには …

源氏物語研究者として、有名な池田龜鑑博士による古典入門書。古事記から里見八犬伝まで21冊を選びだし、数頁の中にエッセンスを凝縮している。一般の人にも古典に親しんでもらいたいという博士の情熱がつたわる。
人生に無駄なことなど何もない。遠回りしてきたように感じることも、それらは全て役立っているのだという言…





友人がMacを買いに行くのにつきあったとき、フォルムと質感に圧倒され、右クリックが無いのは辛いと思いながらも、買うことに決めてしまった。デザインとはなにかについて、様々な角度から解き明かしてくれる。
ジョブズが亡くなって、銀座のMacの前は花束や人で溢れていた。久しぶりにあった同級生たちもその話題で…
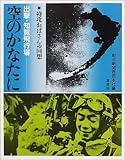
用意周到なアメリカは昭和17年には、戦後処理に関する検討を始めていた。日本では、昭和20年4月に鹿児島県知覧から最書の特攻機4機が飛び立ち、陸軍特攻だけでも1,200人以上の若者が散華した。

ワシントンハイツ、そこは戦後のアメリカ文化を象徴する眩しいところであった。あの恐るべき脱脂粉乳やパン給食をもたらしたGHQの占領軍の将校たちの住まいであったとしても。
ワシントンハイツ。外国人が沢山住んでいて、日本とはまるで異なる世界がそこにあったというかすかな記憶が…

月見座頭:虫の音を聴き十五夜の風情を楽しむ座頭と酒を酌み交わし興じた後、男は声色をかえ、言いがかりをつけ座頭をなぶり去る。座頭とともに荒涼感とした秋の野に立ち尽くす。見てから読むか。読んでから見るか。





ブログをホームページ化することにより、両方のメリットが活せる方法について、懇切丁寧に解説されている。大枠ができた後、ステップアップして、より良いHPができるよう細やかな配慮がなされていることが嬉しい。




富士山の麓の洞穴で、体を捩ったり、捻ったりして、一生出られないのでないかと思いドキドキした経験がある。なんでそんなところに行ったのかって、本書を読み、洞穴とはどんなところかと体験してみたかったからだ。






平易な言葉で、深遠なるモノを語れる人。今ここにいることに集中することがなんという難しいことであり、大切なことか。本物の中に身を浸し、五感を開き自然をあるがままに受け止めること。幸せが溢れている本です。

人間の脳の自動操縦機能を脳が仕掛ける罠だとすれば、そこから逃れるには。罠の自覚さえないとしたらと思うと末恐ろしくなる。行き過ぎた脳の自動操縦を解くための4ステージをクリアした後、リアルをどう生きるか。

石井幹子さんが就職留学したフィンランドを訪ね、照明デザイナーとしての原点をみつめる旅を通し、パッペ先生の凛とした女性の生き方、厳しい自然の中で楽しむ北欧の人々の暮らし方に、清々しいものを感じました。