レンズが撮らえたF.ベアトの幕末





ベアトは英領コルフ島、ギリシャ近辺の島出身の写真家、1834年生まれで1853年のクリミア戦争に写真家として従軍、1858年にはセポイ反乱を取材、1860年アヘン戦争を経て1863年に日本にきた。
当時の日本では一般外国人は開港地の10里以内の外国人遊歩地域しか行けなかったため、スイス外交使節団の…

本が好き! 1級
書評数:151 件
得票数:1084 票
なんでも読んでみようと務めていますが、どうしても興味がある分野にのめり込む傾向があるようです。勤め人時代は通勤電車が読書時間でしたが、退職後は寝る前、昼食後が読書時間、読書傾向も変わってきました。





ベアトは英領コルフ島、ギリシャ近辺の島出身の写真家、1834年生まれで1853年のクリミア戦争に写真家として従軍、1858年にはセポイ反乱を取材、1860年アヘン戦争を経て1863年に日本にきた。
当時の日本では一般外国人は開港地の10里以内の外国人遊歩地域しか行けなかったため、スイス外交使節団の…





筆者は2017年8月の内閣改造で農水大臣に抜擢された元官僚、衆議院当選三回で大臣になった。58歳で大臣になったその人が2002年時点で官僚として執筆していたというので読んでみた。
筆者は1983年に通産省入省、2009年に初当選。将来性を見込まれたのか、神道政治連盟で日本会議メン…





25歳から31歳になるまでの二人の若者の成長物語で、いい感じの読後感が持てた本であった。
本好きが講じて文藝社に入社、入社3年目でそろそろ文藝に関われると思っていたら縁もゆかりもないボクシン…





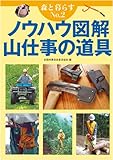
薪割りの必要があり、チェーンソーを買った。薪を割る作業に先立ち、本書を買って参考にした。斧の使い方、危険防止、作業効率、目立て方法など、買ってから作業してよかった。
薪ストーブを導入したのは6年前、燃やすためには薪割りの必要があり、チェーンソーを買った。エンジンと電…





緑と花が庭にあると心が浮き立ちます。従来、好き放題に花や草を買って植えていましたが、少し整理しようと本書を購入。春に咲きだして長く持ち、手入れが要らない、という好都合な品種を探し求めての購入でした。
住んでいる地方や土壌、日当たりなどによって違うと思いますが、長野に住んで3年かかっての結論は、以下の…



「傾国傾城の顔(かんばせ)」という表現があるが、本書の主人公、白草千春はそういう形容がふさわしい美女だった、というタイトルのはずなのだが、感想としては「嫌われ松子の一生」の方に近くて共感できない。
時代は1970年代、美しく生まれてきた千春は13歳まで日本画家だった父親と一緒にお風呂にはいるような…





黒川博行の「繚乱」は「悪果」の続編、主人公は大阪府警退職した堀内と同じく大阪府警を懲戒免職になって不動産調査会社ヒマラヤ総業の嘱託調査員になっているかつての相棒伊達のコンビである。
不動産調査とはいえ中身は競売屋、仕事は入札物件の調査とヤクザなどの占有者排除であり、元暴対刑事にはう…



日本女性トメを頂点とした在日一族高光家の物語。ちょっと不必要に露骨な性描写と、子を生む性としての女性の描き方に違和感を持つ。
大阪で戦前から不動産に投資して、あるときから成功し財をなしてきた一族のお話。その一族は朝鮮半島出身の…





私も自分の親の介護をする世代になり、自分が介護されるときにはどうしていたいかを考えるようになったが、ここまで具体的には考えたこともなかった。自分の親の介護が心配になる世代にはお勧めの図書。
30歳になる市絵は司法書士、広くて取り壊し直前のために格安の事務所兼住居を街の不動産屋を通して紹介し…






通奏低音のように背景に流れるのは、日本に昔いた縄文人とその末裔、山の民「サンカ」と、朝鮮半島から稲作と製鉄技術等とともに入ってきた弥生人とその末裔が共存し、一部分の接触点でつながってきた歴史である。
本書の舞台は出雲の国、島根西部の紅緑村、その昔、たたら製鉄技術で砂鉄から鉄を作り出し生活していた民が…





楽天的、生まれ持っての政治家、相手の懐に飛び込む好かれやすい性格など、俊輔がなぜ百姓から侍に取り立てられ、その後の幕末の荒波の中で頭角を現したかが描かれる。一気に読めてしまう俊輔の成長、出世物語。
1909年、ハルピン駅で暗殺される伊藤博文は周防国束荷村の百姓の子として生まれ育った。名前を利助と言…





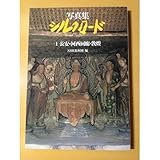
大唐の都、長安を発ち、敦煌莫高窟に至る。歴史を語る莫高窟の塑像・壁画群、炳霊寺の磨崖仏、張掖の巨大な寝仏、長城の西端・嘉峪関、幻の都城・黒水城、これらを再現する。
定価一冊当たり3460円の本がブックオフで1円、送料も三冊で合計750円、神保町までの電車賃や重い本…






手作りスピーカーはいくつか作って、今でも愛用している。元ネタ本は一度手放してしまい、再度入手ができなかったところに、基礎編、図面集として発売されたので手に入れた。長岡ファンにとってはうれしい復刻。
30年ほど前に自作したのは20cmウーファーを前後にダブルで使い、ツイーターを加えたBS-28、それ…






「死刑」、存置すべきか廃止すべきか、という正解のない難しい問題にジャーナリストの森が取り組んだ。
「死刑廃止論者」は、「国家が人を裁くことはできるが、死に至らしめることを強制することは人間の尊厳を損…




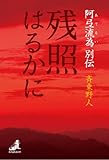
8世紀から9世紀にかけて今の東北地方、当時の陸奥の国、蝦夷の人たちがまだまだ多く住んでいた頃の、都があった奈良、京都の大和朝廷の倭人と蝦夷の勢力を率いていた阿弖流為(アテルイ)たちの戦いの物語である
登場人物は多く、800pにもなる大長編小説である。阿弖流為、小さい頃からの遊び仲間であった母礼(モレ…





マンガは、読む前にはおまけ程度に考えていたが、まだ起きていないことを想像するのに大いに役立つことに気がつく。絵面を見るとヒシヒシと実感を持って、各種事態の切迫度合いとその情景が想像できる。
いよいよ、こういうときが近づいてきた、と感じて読んだ。きっかけは年老いた母の施設入所。まだまだしっか…





リング、らせん、ループと続くリングワールドの続編。いったい、このタイドという物語はリング3部作の続編なのか、プロローグなのか、分からなくなる。
貞子の弟で哲生が生まれ変わった。名前を柏田という。柏田は生まれ変わりだということは認識しているが、貞…





本作は長大な三部作大長編”Age of Misrule”シリーズの第一作。”Darkest Hour"、"Always Forever"と続く、全12作にもなる大長編。その第一作目だけでも630Pにもなる。
第二作は”Darkest Hour"、第三作は”Always Forever"と続く。そして更なる次…





英語人と一緒にいると、仕事では日本人にも分かるように話してくれるが、アルコールが入ったり、ゴルフでは、「おっ!?」と思うような英語に出くわすことがある。それは小中学校で習う数学理科の単語だと気がついた
この本を読んでみたらウジャウジャでてきた。TOEICやTOEFLでも出てこない、新聞でもめったに出く…






この筆者、素人の歴史好きだということだが面白い視点。卑弥呼時代の大王や、魏志倭人伝の邪馬台国がなぜ古事記、日本書紀に出てこないのか、蘇我馬子、蝦夷、入鹿は何者だったのかなど新たな見方を提供してくれた。
卑弥呼の時代の大王は誰だったのか、魏志倭人伝に出てくる有名人や邪馬台国のことがなぜ古事記、日本書紀に…