主人公が、我々のすぐそばにありながら普通は住まない場所に住んでいるという設定の話は、いくつかあります。カルヴィーノの『木のぼり男爵』(1964年)は、もちろん有名ですが、最近読んだ青崎有吾の高校生探偵・裏染天馬シリーズでは、主人公は高校内の元百人一首研究会に住んでいます。実は「私は、浴室で暮らすようになった」という帯のコピーを見たときは、そういう話かと思いました。
本書は、1957年生まれのベルギーの作家ジャン・フィリップトゥーサンが、1985年に発表したものです。初読みの作家で、他の作品は知らないのですが、仏語版 Wikipediaによると、作者のスタイルと物語はミニマリスト、つまり必要最低限の物だけで暮らす人若しくはその生活様式を扱っているそうで、本書にも、それはよく出ていると思います。ただし話というか物語というか、そういうものはない本です。冒頭に述べたように、「浴室で暮らすようになった」主人公がモチーフの本かと思って読みだしたのですが、この主人公、実はあまり浴室にいないのです。そして、最大の特徴は、本来はミステリーのものなのですが、主人公や周囲の状況が始めのうちはきちんと説明されず、話が進むにつれて、分かっていくという進行です。
例えば、主人公「ぼく」と同じアパルトマンに住んでいるパートナーは、エドモンドソンと言うのですが、最初は女性なのか男性なのか分かりません。結局女性だということは分かるのですが、エドモンドソンというのも、普通はアングロ・サクソン系の姓ですし、そもそも姓なのか、名前なのかもわかりません。本書の構成は①『パリ』②『直角三角形の斜辺』③『パリ』と分かれているのですが、エドモンドソンのことを「妻」と他人に話すのは③になってからです。②では主人公はエドモンドソンに何も言わずに、いきなり旅に出るのですが、行き先がヴェニスであることが分かるのは目的地に着いてからしばらく経ってからです。これに類似したことは他にもいくつかあるのですが、結局これが本書を読み進める上で、手助けになっているようです。要するに、次に何が明らかになるか、という興味で引っ張っているとも言えるのです。繰り返しになりますが、これは完全にミステリーの発想です。ですから、何か語りたいことがあるというよりも、どんな人間もいくつも抱えている「謎」が徐々に明らかになっていくプロセスを楽しむ本なのでしょう。ですから、気に入る人は気に入るという類の本です。万人向きの本ではありません。
また、浴室というと、人が裸になる場所であり、フランスではビデがよく設置されています。社会生活において隠したいものを露出する場所と言えるでしょう。結局、主人公が浴室にいる時間はそんなに長くないのに、こういう題名がついているのは、ミステリー風の展開とあわせて考えると理解できます。
なお、映画での浴室に場面というと、私はゴダールの『軽蔑』(1963年)と『気狂いピエロ』(1965年)を思い出すのですが、ホラー映画でもよくモチーフとなっていて、有名なのは『エルム街の悪夢』(1984年)でしょうが、ロマン・ポランスキーの隠れた傑作『反撥』(1965年)でも狂気に陥ったヒロイン(カトリーヌ・ドヌーヴ)が自分が殺した死体を沈める浴槽の場面が印象に残っています。やはり秘密の匂いのする場所なのです。






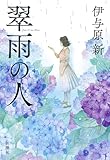


この書評へのコメント