日本シャーロック・ホームズ・クラブ主宰で、シャーロッキアンとして知られる小林司氏と東山あかね氏が書く、ホームズ物語の著者の深層心理を中心としたあれこれ。
第1章は、ドイルのホームズ作品に種々の矛盾があるが、それはドイルがオリジナルの筋書きをヴィクトリア朝の厳しい性道徳に従って書き換えたからだという論考。25か所の矛盾点を挙げ、詳しく分析されているのは「這う人」だけだが、他に「花婿失踪事件」「ボヘミアの醜聞」「まだらの紐」もオリジナルの筋書きはこうだったのでは?とこの章で取り上げられている。「這う人」は簡単に言えば以下のような話である。60代の大学教授の娘の婚約者ベネット青年が、教授の2週間にわたる失踪や奇行の解明をホームズに依頼する。ホームズが調査に乗り出すと、教授は密かに手に入れたサルの血清を回春剤として使用し、再婚に備えていたことがわかる。若い男女の婚約者の他に教授自身が再婚に備えるという、ヴィクトリア朝の性道徳にギリギリ収まる話になっている。著者はこの話を、ヴィクトリア朝最大の殺人事件「切り裂きジャック」とドイルのこの事件に対する推理を絡めてオリジナルの筋書きを推定している。ヴィクトリア朝は性道徳が厳しいが裏では売春やポルノが大流行しており、切り裂きジャックの被害者は皆、売春婦である。「花婿失踪事件」は義父と娘の近親相姦、「ボヘミアの醜聞」も国王が取り戻したい愛人アイリーネとの写真はベッド・シーンの写真ではないか、と性に絡めた著者の推理が披露されている。
第2章は雑多なホームズ論の寄せ集めの感じを受ける。ホームズ物語を通じてのヴィクトリア朝英国文化の理解、ホームズの反権力の姿勢の分析、ホームズと大佛次郎の小説キャラクターの鞍馬天狗の比較、ホームズ物語のカウンセリングの教科書としての読み方、そして日本におけるホームズ物語の受容史である。
第3章は、著者夫妻がロンドンやスイス(ホームズが敵役モリアーティ教授と死闘を繰り広げたライヘンバッハの滝がある)行った旅行記である。たった百年前の物語でも足跡は少なく、読んだ感じだと1970年当時のロンドンの旅行記とあまり変わらない気がするが、夫妻はこの見学を「ヴィクトリア朝の精神構造の理解の足しになった」と結論していた。
第4章は、ホームズ物語の心理的な分析だが、前半は神話構造に絡めたユング流の「ぶな屋敷」と「美しき自転車乗り」の読み解き、後半はフロイト流の著者ドイルの深層心理分析に絡めた「赤毛組合」と「ボヘミアの醜聞」の分析である。
著者はホームズ物語の人気を、ホームズの正義感や、軽い冒険物語だからなどという表面的な理由ではなく、もっと掘り下げた心理的な理由に求めている。「ぶな屋敷」と「美しき自転車乗り」のふたつはいずれも若い美しい女性が、破格な好待遇の家庭教師の仕事を依頼されるのだが、そこには罠が仕掛けられているという話である。ミルシア・エリアーデという宗教学者は神話や昔話は通過儀礼から生まれたことを明らかにしている。通過儀礼は不十分だったそれまでの自己を一旦死なせ、より高い次元の自己に生まれ変わることを象徴している。そして、神話の典型例はエス(本能)に動機づけられた行動や自我の欲求に対して、超自我(良心)がそれを許すまいとする闘いだという。ホームズ物語も悪人(エス)が欲望を抱くのに対してホームズという超自我がそれを打ち砕く話だと要約できる。ここから、このふたつの作品の登場人物に即して、これらの物語の通過儀礼と自己再生についての論が展開される。後半は病跡学という聞きなれない言葉から話が始まる。病跡学とは芸術家の作品などから、その作者の精神的病理を明らかにする学問だというが、病跡学にも問題があり、精神病ではないかとされる芸術家たちと正常人の無意識の分析との比較対象などが欠けているという。これを正常人の例として、典型的な英国紳士であるホームズ物語の著者ドイルに当てはめてみる。彼が結核で療養中の妻ルイズと、その間に交際を始め、後にルイズが亡くなった後に再婚するジーンとの恋に苦しんでいる期間に、その恋の苦しみが作品にどう反映されているのかを示している。その後に「赤毛組合」と「ボヘミアの醜聞」を取り上げている。「赤毛組合」では種々のおかしな点があるが、ホームズへの調査の依頼人ウィルソンがドイル自身の小説中の分身と考えると矛盾点も納得がいくようだ。そうだとすると、この作品は、ドイルが歴史文学者でありたいところ、探偵ものを書かされる大衆作家の地位に貶められている不満や同性愛の傾向を示していることになるそうだ。この分析はローゼンバーグの
「シャーロック・ホームズの死と復活―ヨーロッパ文学のなかのコナン・ドイル」に負う所が大きい。著者もローゼンバーグがこうしたホームズ物語の心理的分析の先駆けと評価している。「ボヘミアの醜聞」の方は、この作品に火事と犯人のアイリーネの結婚が出て来るが、何故これらが小説に登場したのかという分析に充てられている。だが精神分析の専門用語が多用され、それらに括弧書きで簡単な説明があるものの、著者の意図はあまり良く理解できなかった。
題名の通りの深層心理の分析が主の本だが、「シャーロック・ホームズの」ではなく「コナン・ドイルの」とすべきかと思う。深層心理の分析は4つの章のうち1と4のみで2,3はヴィクトリア朝の文化やロンドンとの関連を論じたごく一般的なホームズ論である。それ故、題名との齟齬が生じ、ごった煮の感じを受ける。本書全体としてホームズの新しい読み方を提案してくれたのかもしれないが、2、3章の読み方はそれほど新しいのかな、思う。
文学作品を著者の心理に掘り下げる読み方は、精神分析の始祖フロイトが既に実施している。例えば古代ポンペイと現代を行き来するイェンセンの幻想小説を分析した
「文学と精神分析―グラディヴァ」などである。これをホームズ物で読めるのは勉強になった。しかし、ホームズ物の人気の理由を神話に掘り下げる試みはちょっと失敗かもしれない。どんな物語も神話との関連付けをしようと思えば出来る筈で、神話構造の反映というだけで「ホームズ物」が「聖書」と同じくらい読まれているというのはいささか牽強付会に思える。






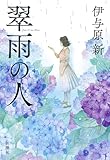


この書評へのコメント