チリとチリリはらっぱのおはなし




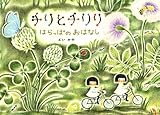
低年齢の子ども向けの絵本。表紙に描かれているのは大きなシロツメクサ。自転車に乗った二人の女の子がチリとチリリ。美しく描かれた、自然にあふれるはらっぱで二人が経験する生き物たちとのやり取りが素敵です。
この本はチリとチリリシリーズの4作目。私にとっては初めて触れるシリーズです。 家のそばにはらっ…

本が好き! 1級
書評数:408 件
得票数:5120 票
言葉は真実を伝えるものではなく、真実の一部または虚構を加工したものでしかない。
「陰謀論にも一理あり」と受け止めることができるようになったことをきっかけに、人の本来のあり方をテーマに本を読んでいます。
https://rubyring-books.site/




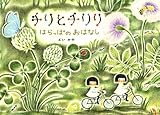
低年齢の子ども向けの絵本。表紙に描かれているのは大きなシロツメクサ。自転車に乗った二人の女の子がチリとチリリ。美しく描かれた、自然にあふれるはらっぱで二人が経験する生き物たちとのやり取りが素敵です。
この本はチリとチリリシリーズの4作目。私にとっては初めて触れるシリーズです。 家のそばにはらっ…





合計2年ほどの日本滞在時にモースが持ち帰り、あるいは譲り受け、米国セイラム・ピーボディー博物館の倉庫に眠っていた彩色写真たち。1枚ごとに場所や年代を記す
この写真集に収められている写真の1枚を説明してみましょう。 60代くらいでしょうか、花売りの老…





松下電工のカレンダー用に集められた素材を元に中南米・アジア・中東・ヨーロッパ・アフリカのめずらしい住まいを収録した写真集
松下電工の創業75周年にあたり、同社が1987から発行している『世界の民家カレンダー』のために集まっ…





魏志倭人伝の解釈に加え、日本書紀、中国の他の史書なども踏まえながら、邪馬台国の位置を無理なく比定
オンデマンド印刷による2022年出版の本です。この本の著者は医師として勤務した後、一線を退き、中学生…





巨大で独特で歴史的価値を持つであろう建造物たちは、しかし、私たちの知るところなく朽ちていくところであった。福島県出身の女性写真家が東欧・南欧の共産遺跡を写す
本書に収められた被写体の多くは、インターネットの画像検索によって確認できるでしょう。 たとえば、「…




イギリスのケルト巨石遺跡の紹介が主で、縄文の話題は少な目。私が知りたかった、ユーラシア大陸の東西両端に広がる環状列石文化(アファナシェヴォ文化)については知れず
最近、アイヌ語を分析した人の動画を見ました。それによると、基礎語の6割を印欧語族系の単語が占める一方…





すべての政治家と、政治活動に携わる人、そしてあらゆる現代人に、今もっとも読んで欲しい本。ロシアとウクライナの戦争や、LGBT・ジャニーズ問題に積極的な左翼の背景が見えてくる。
2014年に出版された本ですが、2023年の今、大きな意味を持つようになった本だと思います。私が今回…




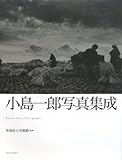
昭和30年代・青森。薄く積もった雪、働く馬、曇り空。
小島一郎は、青森生まれ、30歳頃から写真家としての活動を本格化。一時上京し、カメラ芸術新人賞を受賞す…





火を使い、水を使って穀物や肉を調理し、食べる。気候や歴史が台所空間のあり方に大きく影響する
伝統的住まいの探訪に魅了された建築士が、1982年の建築士会の催しで、それまでに世界各地で集めた資料…





出土品にならって釣り針をつくり、魚を釣る。モリで魚をつく。土器を焼いて使ってみる。竪穴式住居を作る。縄文時代の暮らしがよみがえる。
縄文時代に使われていたという釣り針を見て、本当にこんな大きな針で魚が釣れたのだろうかと考えたことはな…




ウィスコンシン州に住む15歳の少年と7歳のオオカミは、小さい頃からの間柄。けれど、事件が起こり、オオカミは逃走。追手からオオカミを守りながら安全な森まで送り届ける冒険が始まる。
1976年初版、原書は1970年発行。米ウィスコンシン州を舞台に作られた物語です。 幼くして人…





種から育てた鉢植えのタンポポをうさぎくんからもらったライオンはかせ。いいことを思いつきますがとんでもない結果に。
小さい子ども向けの絵本ですが、遺伝子組み換えによる植物の作り替えに対して、「それはいいことではないよ…





今回のパンデミックはPCR検査が作り出している
本を一通り読み終え、最初に戻って、扉の次に記された2行を読む 中国武漢から世界に広がったのは、ウ…






哲学者が生物の研究を通じて心を探究したこの本は、見逃していた不思議に目を向けさせ、生物である自分を再確認させてくれる
この本はある意味、脳の発達に的を絞った『 新・人体の矛盾 』であると言えます。哲学者としての視点から…




個性と才能の豊かなメンバーを束ね、企画力と、会話の面白さ、編集の巧みさで視聴者を増やしてきた東海オンエアのリーダーが、天才と称されることもある自身について振り返る
東海オンエアというユーチューブ・グループを知ったのは、彼らが活動を開始して登録者数が数十万人になった…





日本語は遥か南の海のかなたから弥生文化とともに運ばれてきたとする、日本語タミル語同系論を検証する
1989年に開催された、言語学者大野晋氏の主張する南インドのドラヴィダ系言語であるタミル語と日本語が…





古代史専門の学者が出雲を訪ね、神話の舞台を肌で感じながら、まるで出雲出身の郷土史家が描いたような贔屓目を通じて、大和とは違う神話を持っていた出雲を語り、モノクロ写真が現地の雰囲気を伝える。
先日、愛知県の渥美半島の先端にある、伊良湖岬に行ってきました。島崎藤村の椰子の実の歌で知られた浜があ…






エンジニアとしての経験に基づいて事実を積み上げながら歴史を紐解く手法は、推理小悦を読んでいるような興奮をもたらす
私は日本の古代史に詳しくなく、この本に書かれている時代についてもあまり知識はありません。けれど、どう…





東アジアの複雑な歴史を象徴するような、大阪府ほどの大きさの島、済州島の古代文化を、島にルーツを持つ著者が探る
弥生時代の直前に当たる春秋時代(紀元前8―同5世紀)から前漢時代にかけての江蘇省の人骨と、渡来系弥生…





当初1979年発行された、30年にわたる調査・取材をまとめた狩猟民としての山人「マタギ」に関する現場主義的事典
この本は体系立てて編集したり、解釈を加えた性質のものではなく、秋田魁新報社に勤めた著者が長年にわたっ…