世界国勢図会-世界がわかるデータブック(2014/15年版)
![]()






統計集ですから、その数字を眺めているだけなら、無味乾燥です。しかし、問題意識を持って数字を追いかけていくと、無限のヒントが浮かび上がってきます。
この本を1冊、目を通すだけでいい。今、書店の店頭に並んでいる安直な新書数冊分の内容が読み取ることがで…

本が好き! 1級
書評数:202 件
得票数:722 票
朝日新聞の記者です。
![]()






統計集ですから、その数字を眺めているだけなら、無味乾燥です。しかし、問題意識を持って数字を追いかけていくと、無限のヒントが浮かび上がってきます。
この本を1冊、目を通すだけでいい。今、書店の店頭に並んでいる安直な新書数冊分の内容が読み取ることがで…
![]()






地に足が付いた知識の宝庫です。1927(昭和2)年の初版以来、この本で72版。「本書に書いたことは何科の生徒にでも教えたいと思うこと」と初版序文に記した創刊者の意思が今も生きている。
この本を読むのは38年ぶりだ。 高校の地理の授業で使って以来のことになる。 当時、地理の恩師は「…





スポーツをネタに縦横無尽に筆を進めた随筆集。スポーツはやって楽しく、見て楽しく、話して楽しい--それを実践したのがこの1冊。
スポーツをネタに縦横無尽に筆を進めた随筆集。 元々はナンバーの連載だったという。時期とすれば前回の…




拾い読みもよし、通読もよし。日本語を再考する手がかりになります。
1篇2~3ページほどの掌編が続く。 拾い読みもよし、通読もよし。気楽な読み物であり、おお、と思うこ…




国文専攻の授業のような内容です。定家本土左日記を題材にした授業を思い出してしまった。
国文専攻の授業のような内容です。 定家本土左日記を題材にした授業を思い出してしまった。 国文…
![]()





入浴をした温泉の数の多さ、で温泉を語る。新しい試みの1冊。数の力がもたらす説得力が魅力の1冊だ。
統計を取る場合に、標本調査と全数調査(悉皆調査)という2つの手法がある。 ご存知、世論調査などは前者…






新しい社会的ネットワークで危機の時代を乗り越えようという今、中世以来の「一揆」の構造を見直す値打ちがある、と筆者は説く。
この1冊の最初に掲げられている「戦後民主主義の中で血縁や地縁といった縁はネガティブに評価されてきた。…





ステロタイプの台本を脱却したのが価値。タマキングの処女作は今も新鮮。
筆者の処女作。 ことの運びではどこか若書きとも思えるけど、何か新鮮。 何が一番秀逸と思う…




現行憲法の生みの親の一人である筆者の解釈注釈は制定当時の人間の意を汲む上で参考になる。
明治憲法の解釈の根本資料としては伊藤博文の「憲法義解」がある。何で、伊藤博文の憲法義解を出したかとい…





天皇の葬送儀礼を綴っていくことで、日本という国のある一面をプレパラートに載せることに成功した本。
天皇の葬送儀礼を綴っていくことで、日本という国のある一面をプレパラートに載せることに成功した本。 …





日本史の教科書で習った知識で言えば、ほんの数ページで納められてしまうような、元寇から応仁の乱までの間ではあるけど、実はかくも国内が激動していたのかと蒙を啓かれる思い。
日本史の教科書で習った知識で言えば、ほんの数ページで納められてしまうような、元寇から応仁の乱までの間…





歌舞伎の舞台に登場するタバコ、酒、水の名場面を取り上げ一篇の随筆に仕立てた作品集。
歌舞伎の舞台に登場するタバコ、酒、水の名場面を取り上げ一篇の随筆に仕立てた作品集。 日本たばこ…




「人間、おっさんともなれば寂しさと自己顕示欲が制御しきれない」というのは冷徹な事実かもしれない。
会社の元上司、仕事仲間の3人で出掛ける温泉紀行。 常々、他の著作では、服を脱いだり着たりするの…




旅随筆というか、珍道中記というか、結局は所謂「タマキング」ワールドなのだけど。
最初から書籍になることを想定した書き方と、Webで連載の書き方とは自ずと異なる。 その点でこの…



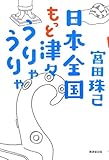
自分がすでに行ったことがある土地でも、筆者とは目の付けどころが違い過ぎて、目から鱗。
本篇より先に続篇を読んでしまった。でも何も齟齬を来すところはない。 編集者とともに全国を経巡り…
![]()




囲碁の布石からの変化の解説本。一種、ロールプレイングゲームのように話を展開していくのが新鮮。
囲碁の初心者向けの入門書です。 筆者は韓国のプロ棋士で今はハンガリーで普及に努めているよし。 書い…




見坊豪紀と山田忠雄。一国一城の主が見せた、攻防戦を活写した1冊である。
見坊豪紀と山田忠雄。 三省堂が発行している2種類の国語辞典の作成に関わる話である。 NHKの番組…
![]()



小説の中身より、稀代のプロデューサーといわれた蔦屋重三郎という人物をどう描くかが興味津々。さて、筋立てとしては上々だけど、最後に「ご教訓」をつけたのはやり過ぎ。
小説、というか、読み物としてはおもしろい筋立てです。 勧奨退職となった会社員がタイムスリップして江…




やっぱり筒井康隆はすごい。ただ、何度でも書き直しが世に問われそうな「遺言」だ。
筒井康隆はすごいと思う。 ここまで自己分析をしながらものを書くということを書いているということ…





京都の老舗金物店、有次の包丁を取り巻く人々を点描することで日本の手仕事、精神性、人間関係の機微を書いていく。
有次といえば京都の調理器具店。 打ち出しの鍋、網、おろし金、そして包丁が名高い。 東京の…