日本の近代とは何であったか――問題史的考察





アジアでなぜ日本だけがいち早く権力分立体制、議会制を導入できたのか? 直近の世界情勢を見ると、トランプ・アメリカの未成熟さが浮かび上がる内容でもある。
政治外交史が専門で現在も東大名誉教授の著者が八十歳代になって執筆したもの。 本書のヒントをウォルタ…

本が好き! 1級
書評数:455 件
得票数:6611 票
仕事、FP活動の合間に本を読んでいます。
できるだけ純文学と経済・社会科学系のものをローテーション組んで読むようにしています(^^;
相場10年、不良債権・不動産10年、資産形成(DC、イデコ)20年と、サラリーマンになりたての頃は思っても見なかったキャリアになってしまいました。





アジアでなぜ日本だけがいち早く権力分立体制、議会制を導入できたのか? 直近の世界情勢を見ると、トランプ・アメリカの未成熟さが浮かび上がる内容でもある。
政治外交史が専門で現在も東大名誉教授の著者が八十歳代になって執筆したもの。 本書のヒントをウォルタ…





現地参謀の暴走によって、不毛で経済価値が乏しい広大な国境地帯で起きた小競り合い。 これが第二次大戦の火ぶたを切ることになった。
著者は全編を通し、執拗に、そして感情的に非難の矛先を、関東軍の 「辻政信」 個人に向けている。 こ…





凄いと思うまで三回以上読み直す必要があった。直木賞受賞作でなければ、読むのをあきらめたかもしれない(長文注意!)
主人公は 樺太(サハリン~ここでの表記は樺太に統一) の地で旧ロシア帝国と日本の間で翻弄されながら生…





平戸松浦藩に連なる由緒ある家柄、普通部経由の慶応ボーイの兄弟。雲の上、別世界の人種の彼らがバブル期、歴史的な政治・経済の動乱の中心にいた。
「バブル兄弟」はぴったりのタイトルだけど、サブタイトルは「やりすぎ」かも。 バブルピーク株価は…





ユダヤ系アメリカ人、エルサレムに住んでいる著者が、パレスチナの人々についてここまで書いたことに敬意を表したい。
ユダヤ人に負い目があるドイツの首相まで「理解不能」と言わざるを得ないイスラエルの昨今の状況。 …





この人の作品を読んで思うのは、「最後はひとりぼっち」という人間の本来の姿なのだが、ラストは鮮やか!
「風の歌を聴け」から続いている作品群のひとつと言われるが、「羊をめぐる冒険」の続編と言ったほうがしっ…





事業譲渡、M&Aについて何冊か読んだ中で、素人視点ではあるけど、十二年前の本書が一番面白かったのだ。
企業の事業譲渡、ここ数年の間、中小・零細企業でニーズが急拡大している。 にもかかわらず、世の中のサ…




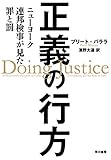
トランプがトップになる国。司法はどうなってる?……が動機だが、見えたのは全く違う風景だった。
著者のプリート・バララは元ニューヨーク連邦検事。 2009年にオバマ大統領(当時)に任命され、20…





「羊をめぐる冒険」以前の作品の情報を積み上げないと流れが見えない点では、これらはセットのストーリーなのだろう。
何も考えずに手にとったため、タイトルから「羊」シリーズの続編とは想像できなかった。 「僕」は今…





大都市圏の「家」に対する見方、考え方がわかりやすい。都心部で高さを求めて発展する街の姿はもうすぐ転機を迎えるだろうが、その後に来るものは何なのか?
著者の牧野さんはボストンコンサル~三井不動産~日本コマーシャル投資法人(J-REIT立ち上げ)……日…




子どもの頃からアシモフのSFものが好きだったため、思わず手に取ったが迷路にはまり込んでしまった。以下長文注意!
本書については、この分野の大先輩お二人が書評を書いていらっしゃることもあり、いつか読むべき本だと思っ…






春樹という色眼鏡を通さずに読むほうが良い。作品の正体は、素直で切ない純愛小説だった。
実は二十代前半のころ購入した、本書の初版本が本棚にある。 そのとき、最初の数十ページをめくって「文…




得体の知れない巨大国家のイメージの中国。実は今、不動産依存経済の矛盾が国を歪め、ぼろぼろの状態。打開策として可能性が高いのが台湾侵攻?
ほんとう?と思いながら読んだ。 高橋洋一さんと、四川省出身で北京大学卒、今は日本国籍の石平(せ…




なるほどの部分と、ちょっと違うなと思う部分がある。当局の組織、問題点が見えすぎるため、森を見ない的な、素人に誤解を与えかねない内容になっているかも。
著者は僕より一歳上で、東大卒、読んで初めて知ったが卒業してから専売公社に就職。 そこで当時の大蔵省…






世界で流れているパレスチナ~イスラエルに関する情報は、欧米のフィルターがかかっているかも。
日本人はキリスト教、ユダヤ教、イスラム教との関連は薄く、パレスチナについては欧米より客観的に見れると…




両極端の人生を辿ってきた日本とアフリカの二人の女性。住人のほとんどがアングロ・アイリッシュの海辺の小さな街に、二人が溶け込んでゆく童話!
凝った味の清涼飲料水という感じ。 育った農地を追われ17歳から8年間、アフリカの紛争地帯を点転…





日本人として心情的に深入りしたくないテーマ。買うのを躊躇したけど、辛くても読まなくてはいけない本かもしれない。
書店で手に取った時は不愉快だった。 太平洋でアメリカにぼこぼこにされ、無防備だった満州に火事場泥棒…





なんとも言えない不思議な魔力を持った作品集。図書館の本棚に飾られていたタイトルを見て、誘われるように借りて読んだ。
本書で描かれる「タンゴ」はイベリア半島で生まれ、ブエノスアイレスで発展した、「アルゼンチンタンゴ」。…





一時的な処方箋のはずだった円安が麻薬となり、根本的な解決に乗り出せない政府。今はダイナミックな政変で既存の概念を破壊する時期なのかもしれない。
本書では触れられていないが前FRB議長バーナンキが退任後の2015年に語ったことば。 「金融当局…





読んだのはオリンピックがきっかけだったけど、そもそもの出発点は佐藤賢一さんの暗黒面のフランスなのだ。
本書を僕は、歴史本として読み、観光案内的な部分は深読みしなかった。 最後の二章ではパリがヨーロ…