手塚治虫「戦争漫画」傑作選





「もう結構。これはこの世の現象じゃない。作り話だ。漫画かもしれない。おれは、その漫画のその他大勢のひとりにちがいない。それなら早いとこ終わりにしてもらいたい」空襲後焼死体転がる中を帰宅した作者の述懐。
本書の存在は前から知っていましたが、拾得さんの書評がきっかけで、読んでみました。考えてみれば、手塚治…

本が好き! 1級
書評数:2323 件
得票数:44530 票
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。





「もう結構。これはこの世の現象じゃない。作り話だ。漫画かもしれない。おれは、その漫画のその他大勢のひとりにちがいない。それなら早いとこ終わりにしてもらいたい」空襲後焼死体転がる中を帰宅した作者の述懐。
本書の存在は前から知っていましたが、拾得さんの書評がきっかけで、読んでみました。考えてみれば、手塚治…




ディーノ・ブッツァーティの日本編纂の短編集としては、三冊目の本です。
ディーノ・ブッツァーティの日本編纂の短編集としては、『七人の使者』『待っていたのは』に続く三冊目の本…






軍政下のナイジェリアから身の危険を逃れるために、英国に送り込まれ、難民となった姉妹の子供たちを描いた本です。二人は苦労するのですが、不備は多々あれど難民受け入れの制度が整っている英国の姿が印象的です。
1943年に南アフリカに生まれた作者ビヴァリー・ナイドゥーは、反アパルトヘイト運動に係わったことによ…





「頭のなかに、自分の声以外なにもないまま年をとるということは、おそろしくつまらないからよ。もう少し穏やかな言い方をするなら、退屈ということ」(本書登場人物の台詞)
ぱせりさんの書評で、本書のことを知りました。感謝いたします。 大英帝国華やかりし頃に、海外に生…






表紙に描かれているのは、インド洋モーリシャス島に住んでいたモーリシャスドードーです。飛べない鳥で、人間の乱獲や持ち込まれた天敵(ネズミ等)の捕食により1681年に絶滅したとされています。
2026年1月1日発行のビッグ・イシュー誌518号に載せられていた、2025年刊の本書及び作者の森洋…




「わたしのお尻ってそんなに大きく見えないじゃない、っていうかそもそも大きくないよね、とか自分に言い聞かせてるんだ。わかる。 でも本当は大きい。それが問題だ」(本書収録『それって欲張り』より)
本書のことは、たけぞうさんの書評で知りました。感謝いたします。もっとも、書評を読んでから実際に手に取…






「人類にとってもっとも根強く、もっとも心休まる幻想のひとつは、『ここで起きるわけがない』―自分自身の生きるささやかな時と場所は、大変動だとは無縁だという信念にちがいない」(本書より)
イギリスのSF作家ジョン・ウィンダム(1903-1969)が1951年に発表した処女長編作です。H.…




「自分の人生は自分が作っていくものだというのがわたしの信念だし、自分の人生はそうしてきた。どれほどの価値のある人生かはともかくとしてだ。そして自分の人生には完全に責任を負う」(本書より)
本書は、1952年にオスロで生まれた作者ペール・ペッテルソンが2003年に発表したものです。これまで…





「筒井康隆は筒井康隆であって、それ以外の数十億の人類のだれでもないのだ。筒井亜流が出現してもよさそう(中略)だが、おそらく永遠にあらわれまい。彼の個性の独自さである」(星新一による本書解説より)
本書は、元々は三一書房から1968年に出版されたもので、1972年に角川文庫化されました。Wikip…




「ドイツ人があんなことをしなかったら、ユダヤ人がパレスチナに帰ることもなかったはずだ。それが、今じゃあ、連中の新しい国ができようとしている」(1947年のヨーロッパを舞台とする本書の登場人物の台詞)
「本書にはまた、グレアム・グリーンの名作中編小説(というより、キャロル・リード監督の名作サスペンス映…






「あるときはパリで、ふと気づくと彼女を探していた。彼女がヨーロッパのどこに住んでいるのかまったく知らないのに、なぜこんなことをしているのだろうと彼は思った」(本書収録『1月』より)
ぽんきちさんと、ぱせりさんの書評で本書のことを知りました。感謝いたします。 1962年にアスル…





本書収録作の中では、一人称、二人称、三人称をその特徴を活かして駆使し物語を展開した、ロバート・シルヴァーバーグの『太陽の踊り』が秀逸でした。
全6巻の20世紀SFシリーズの第三巻、1960年代の14作が収録されています。この時代は、小説も映画…




何も起こらない日常でも、時には何か起こります。でも、それも含めて、やっぱり日常なのです。
本書のことは、ぱせりさんの書評で知りました。感謝いたします。 作者の小沼丹(1918-1996…






ヌーヴォー・ロマン若しくはアンチ・ロマンの旗手の一人ミシェル・ビュトールの長編小説作家としての集大成です。作者は本書をもって長編小説を書くのを止めてしまいましたが、必然的な結果だったのかもしれません。
皆さま、明けましておめでとうございます。昨年中はいろいろとお世話になりました。今年もよろしくお願いい…






「『どうだったい、辛かったかい、あっちは』 おっ母さん、そんなことをきいて、僕はなんと答えたらいいんです。お話しても、あなたにはおわかりになりません。また決しておわかりにはなりますまい」(本書より)
1929年刊の本書は、第一次世界大戦をテーマとした小説としては、おそらくもっとも知られた小説でしょう…




慈善と偽善は紙一重。
上下巻(文庫本四冊相当)通してのレビューです。 チャールズ・ディケンズ(1812ー1870)は…




殺し屋と娼婦というのは、昔から映画監督の好きな職業です。
殺し屋と娼婦というのは、昔からいろいろな映画に登場してきたキャラクタです。ただ、娼婦が主役を張る映画…




表題作『倒錯の庭』が群を抜いて素晴らしい短編集です。ただ、その他の3編はいささか物足りなさが残ります。
小池真理子(1952年生まれ)は、私の好きな日本の怪奇小説作家の一人と言っていいでしょう。このサイト…





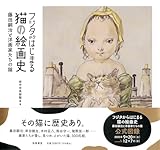
先日、府中市立美術館で開かれていた「フジタからはじまる猫の絵画史 藤田嗣治と洋画家たちの猫」を観てきました。本書はその公式図録です。
現在の私は福島県の片田舎に住んでいて、別に日常生活に不便を感じることはないのですが、映画館や美術館に…




『昼顔』『影の軍隊』の作者ジョセフ・ケッセルが描く、妻を殺した男と、夫を殺した女の恋物語。
1954年に出版された本書の作者ジョセフ・ケッセル(1898-1979)は、父親は現リトアニア(当時…