山本五十六




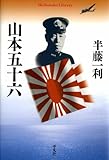
今冬公開された映画『山本五十六』の原作。五十六の後輩にあたる半藤さんの著作のため、やや五十六びいき、長岡偏重気味に書かれた本である。五十六が大好きで、長岡大好きな僕にとっては何の問題も無いですが(笑)

本が好き! 3級
書評数:33 件
得票数:30 票
将来高校の教員になることを目指して
大学で学んでいるTOMです。
内田樹/東野圭吾/村山由佳/赤川次郎
などを中心に読んでいますが、
それ以外の本もどんどん読んでいきたいと思います!




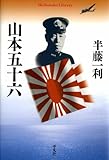
今冬公開された映画『山本五十六』の原作。五十六の後輩にあたる半藤さんの著作のため、やや五十六びいき、長岡偏重気味に書かれた本である。五十六が大好きで、長岡大好きな僕にとっては何の問題も無いですが(笑)




消費税増税(というより消費税そのもの)に断固として反対する立場から書かれた一冊。極端な論であるためその全てを鵜呑みにすることは出来ないが、意外と知られていない消費税の仕組みを詳しく知るためには役立つ。




金融・財政に関する事柄が幅広く解説されている。この本一冊読むだけで経済のニュースがわかりやすくなるのではないだろうか。参考文献がほとんど記載されていないのが、少し残念。参考文献なくても書けるのかな…




山本五十六を語るためには必読の一冊。五十六の欠点と思われるような部分も、著者は「人間味」とし、却って肯定的に捉えている。五十六と関係のあった人への取材を軸に、戦争突入前の五十六の姿を詳しく記している。
太平洋戦争開戦70周年を記念して、2011年12月23日に公開された 映画『連合艦隊司令長官 …




『天地人』の作者として有名な火坂さんの本。室町時代から江戸時代にかけての武将の格言、名言、そして迷言(?)がテーマごとにまとめてあり、非常に読みやすかった。






まずは新潟弁が主体となっている文体に引きこまれた。主人公の「烈」という名前の由来、父の苦悩、家族間の葛藤、そして烈の成長… それらが複雑に絡み合いながら、物語の引力となっている気がする。






上巻と比べてストーリー展開が加速している印象。主人公の波乱万丈な生涯と、それとは対照的な穏やかな締めくくり。本のタイトルが『蔵』になった意味がよく分かる。最近読んだ本の中では一番良かったかもしれない。





「敗軍の将」とも言われかねない立場の山本五十六はなぜ英雄視されているのか、という問題意識をベースに書かれた本。あの有名な真珠湾攻撃などよりも、そこに至るまで五十六が辿った道に焦点が当てられている。





前半の「ウチダ式教育論」には、毎度のことながら納得させられる。特に、学校や教師に権威を見出さない親の問題点についての論は見物。後半の『虞美人草』『こゝろ』を引用しての漱石論も興味深かった。

本書全体を通しての筆者の主張(教育を経済的側面から見過ぎ?)には違和感を禁じ得なかったが、部分部分の意見には納得させられることが多かった。学校教育について、理詰めで考える際に参考になる本かと。





「たまたま同じ場に居合わせたものが共に作っていく場」としての公立学校、という考え方に共感。学校が直面する諸問題を「処理的」に扱うのではなく「研究的」に扱うことの大切さに気付かされた。

高校時代に読んだ本を再読。日銀を知るだけで経済のすべてを理解することはできないとは思うが、「日銀」という1つの軸を定め、その軸にそって経済を学んでいくという手法は、経済を理解する大きな助けになった。




北方四島・竹島・尖閣諸島等、日本が抱える領土問題を主に明治期まで遡り解説。これらの領土問題に対しては、それぞれ異なる解決方法が必要と著者は主張。「固有の領土」という言葉に潜む罠について考えさせられた。




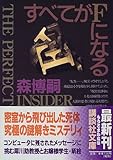
初めて読んだ森博嗣の小説。前半は難解な言葉と状況設定に混乱しながら読んでいたが、途中から徐々に張られていた伏線がつながり始め、犯人が分かった後でさえも、その論理展開とドラマ性に圧倒された。




たしかに前作の方が面白かった気もするが、やはり作者の回答の切れ味は今回も健在だった。相手に「問い」を持たせていくこと、このことは作者が意図している/していないに関わらず、教育的に作用していると思う。

田中角栄元首相の秘書が書いた1冊。越後長岡という雪に閉ざされた地域が生み出した悲劇の偉人達。特に角栄の「裏日本」にかける想いがひしひしと伝わってきた。上越新幹線の列車名が「あさひ」だったことにも納得。


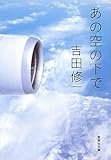
ケニアに行く飛行機の中で読んだ。文体はそんなに好きではないが、旅が好きな人にはたまらない一冊かも。なんだかんだで、俺も旅に出たくなったし…




1巻目に比べると、かなり一般受けする軽い展開になっている印象。それでも後半のペリーとのやり取りには引き込まれてしまった!




3巻当たりから出てきた「それはちょっと…」的な部分も前半には残っていたが、この巻の最後の方には圧倒された。果たして寧温の琉球に対する想いを、俺たちは受け止められているのだろうか?






常に相対的にしか自分たちを見ることができない日本人。一見ネガティブな見方ではあるが、そこから日本人が得ている物の数々を内田樹が解き明かす。内田氏の日本、教育、宗教についての持論が詰め込まれた1冊。