薔薇のなかの蛇
![]()




続編を期待していいですね? でも17年後は無理!
最近、小説が読めない。年齢のせいだろうか。 作りられた物語ではなく、どんなに凡庸でも実際に起きた出来…

本が好き! 1級
書評数:72 件
得票数:1583 票
今まで読むばかりの読書、少しはかたちに残してみたい。
未知の感情を体験されてくれる本、あらすじを説明できないような本が好きです。
勢いで大学の通信部の史学科に入学。歴史の本の合間に良質な物語も読んでいきたい。
![]()




続編を期待していいですね? でも17年後は無理!
最近、小説が読めない。年齢のせいだろうか。 作りられた物語ではなく、どんなに凡庸でも実際に起きた出来…




多様性を受け入れて生きるのは幻想かもしれない
時間的余裕がない時に、図書館の予約が回ってきた。 延長できないので、かなりすっとばして読みました。…
![]()





遠い場所ならば未知なのではない。一番近くて、遠い街--江戸を歩くためのガイドブック。
旅、というと、なぜか遠くに行きたくなる。遠くであれば未知の場所であるように思う。 でも、過去だっ…





凡人が到達する実感に、賢人も至る
著者の本業での著作は難しくて正直理解できているとは言えないけれど、本書を読んで「若い時に成功してし…



結婚という形態の縛りはかくも強い(のか?)
著者は「恋愛には興味が持てない」「恋愛に向いていない」と自身を分析する。 けれども、一人きりの…





すてきな1年を私も一緒に過ごしたよ
結婚生活が行き詰まり、夫と別居中であった花田さんは、深夜のファミレスで強く思う。なんて自分の世界は狭…
![]()





戦後を三つの時代に分け、各時代からそれぞれ20作品を紹介。純文学から大衆文学まで幅広いラインナップで戦後の世相を文学から眺める。 ブックガイドではなく本格的な「文芸評論集」
500頁近い大著です。執筆者も大学関係者や文芸評論家など、かなり硬派な作りです。 このような硬質な本…




「呪いの言葉」からは逃げるが一番!
「嫌なら辞めればいい」「デモで何か変わるの?」「不快な思いをさせたとしたら」などなど、正当な権利を封…





日本人、平成にはいろんなものを食べてきました
流行の背景をあれこれ考えるのは楽しい。現在進行形のことは正解などないのだから、思いつく要素を上げてみ…





名著・奇書を「辺境眼」と「中世眼」で読んでみたら。なんとも楽しい読書会。
『世界の辺境とハードボイルド室町時代』の続編。 今回はお互いが読む本を提案し合って、その読書会を行…




かなり手こずりました・・・。再読は無理だけど、所々、拾い読みしたい文章がたくさんあった。
通信大学のレポート課題本。 歴史の随筆では必ず出てくる本なので名著なんでしょう。1962年に出版さ…



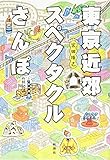
宮田さんは「歩く人」
緊急事態宣言が出ていた時期、宮田さんは散歩をしまくっていたそうで。 SNSに散歩で見かけた風景をア…






「食べることと出すこと」ができなくなった時、身体からはさまざまな訴えが。「経験しないと分からない」という分断を受け入れる。
ラジオで聞いた著者・頭木さんのお話がとても素晴らしかったので、手に取りました。 潰瘍性大腸炎は…





「グッバイ、Google。ハロー、風景」(by 坂口恭平)
坂口さんのパステル画を目にしたのは、Twitterのタイムライン。 以前『独立国家のつくりかた』を…



![波 2020年 11 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41gwa6spGeL._SL160_.jpg)
ちんたん、最高。タッ(名前です。九ヶ月赤子)は歩けるようになった(※仮)
すみません、PR誌、連続で。好きなんですよね、PR誌。 『波』の連載は上質なものが多くて、昔は…




![本の窓 2020年 11 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51E1P4CRIdL._SL160_.jpg)
川上弘美さんが赤裸々に「専業主婦であった時のこと」を語っています。お金と伴侶の無理解についても。必読&永久保存。
紙での発行の最終号。WEB、絶対に忘れるって。 それはともかく。 川上弘美さんのエッセイには…





路上にはみだす植物愛。みんな、見て行ってー。
散歩をしていると思い思いに工夫を凝らした園芸成果を見かける。 ご本人はけっして奇をてらっているので…





お前たちは道具がなければこの山を登れないのか? と平安時代のファーストクライマーは言った
明治時代、日本国土の測量を推進するために、当時未踏峰だった北アルプスの剱岳に挑んだ日本陸軍の測量部・…





研究者たちに幸あれ(笑)
とにかく、読んでいて楽しい本です。 研究者が詠んだ「あるある川柳」がイラストと共に掲載されています…






元禄時代の人々は綱吉と浅野内匠頭という二人の荒人神を一方は仇討ちで慰め、もう一方は歌舞伎で呪詛していた
すっかり歌舞伎という芸能が縁遠くなってしまったので、昔の人々が歌舞伎をどのように観ていたのか実感する…