蜜のように甘く





「あれほど幸せだったことはそれまでに一度もなかった。あれほど幸せだったことはそれからも一度もない」『幸福の子孫』より
短編作家イーディス・パールマンの邦訳2冊目の短篇集。掲載された10篇のどれもが、無駄のない、簡潔な文…

本が好き! 1級
書評数:69 件
得票数:905 票
備忘録がてら、読んだ本のメモを書くことにしました。
翻訳もののSF/幻想小説系が好きですが、それ以外も
チラホラと。





「あれほど幸せだったことはそれまでに一度もなかった。あれほど幸せだったことはそれからも一度もない」『幸福の子孫』より
短編作家イーディス・パールマンの邦訳2冊目の短篇集。掲載された10篇のどれもが、無駄のない、簡潔な文…






「わたしに言えるかぎり、それがあまりできの良くないドラマだってことだ」本文より
私はトレッキーではないので(どっちかというとスターウォーズ派)、表紙を見ても「銀河ヒッチハイクガイド…




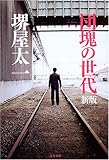
「先のことを考えないで、福祉だとかレジャーだとかで民族のバイタリティーをことごとくその日の商品に使ってしまった責任世代なんですよ」『民族の秋』 より
評者は未来予測が好きだ。特に、少し昔の、既に通り過ぎてしまった時代を予測したものを読んで、あたってい…
![]()





「道路の中央に停車してるパトロールカーは、巨大で黒い三匹の犬が集められた羊たちにとびかかろうと構えているようだ。悪意に比べれば、無関心など何だというのか。」本文より
ラヴクラフトの自身のNY生活時代を題材にした短編「レッド・フックの恐怖」を下敷きに、彼が嫌悪した黒人…






「『麻酔なしだな』と彼は言った。『なぜだ』『化膿しているからね』町長は歯医者の目をじっと見た。『わかった』と言って、彼は笑顔を作った。」<ついにその日が>より
ラテンアメリカ文学の代表作の一つ「百年の孤独」の著者、G.ガルシア=マルケスの中短編を、ラテンアメリ…




「なんでも買ってやる。人間も、歴史さえもだ」本文より
第二次大戦中にフィリピンで戦死した詩人、竹内浩三。彼の未発見原稿を探して、主人公の須藤はフィリピンを…






「団地はまだ暗かった。これほどに巨大な闇ははじめてだ。テオは商店街から吐き出される光の下から黒い団地を見あげた。自分は光のもとにあり、ユジンは闇の中にひとりいることが奇異に感じられた」本文より
平凡な日常を描いているはずなのに、いつの間にか悪夢のなかをさまようような、そんな作品が並ぶ短篇集。9…





「ことばは沈黙に 光は闇に 生は死の中にこそあるものなれ 飛翔せるタカの 虚空にこそ輝けるが如くに」「影との戦い」より
ファンタジー王道ともいうべき前半3作と、同じ世界を全く違う視点で書き直した後半3作からなるファンタジ…





「道化:こんな寒い晩は、だれだって阿保や気ちがいになってしまうんだな」本文より
言わずとしれたシェイクスピア四大悲劇のひとつ。王様が三人の娘の姉二人に追いやられ、三女が味方するのだ…






「トニーは目を開けなかった。他人の苦しみがよくわかるなどと言う人間はみんあ阿呆だからだ。」[エンジェル・コインランドリー店]より
単行本としては初訳となるルチア・ベルリンの短編集。アメリカでも現在再評価が進んでいる作家で、リディア…





「我々はぐるりと回って、原点に戻ってきたのではないか?」著者後書きより
「ディオゲネス変奏曲」を先に読んで、こちらに流れてきました。イギリス統治時代末期のの香港を舞台にした…



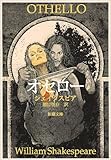
「イアーゴー:~中略~一方、おれは――おお、神よ、人もあろうに!――ムーア御前の旗持ちだ」本文より
言わずと知れたシェイクスピア四大悲劇のひとつなのだが、戯曲を読むのがあまり得意でなく、シェイクスピア…





「きっとひとりの作家からすれば~中略~木桶の中にこもって自分の好きな物語を書くことのほうが心の満足を得られるのだと思っている」著者後書きより
昨年の本屋大賞翻訳小説部門の第2位だった「13・67」の著者、陳浩基(サイモン・チェン)の最新短編集…






「事実に基づいて世界を見れば、世の中もそれほど悪くないと思えてくる」本文より
インターネットの発達で、情報は以前と比べ格段に入手しやすくなった。にも関わらず、我々は依然として世界…
![]()





『どうやらわたしのゴーゴリ病は、ご覧の如く「死に至る病」であったらしい』後記より
小説家・後藤明生による、ニコライ・ゴーゴリについてのエッセイ集。 雑誌や全集の月報など、各所に掲載…





『もし人間がほんとにコミュニケーションを望んでいるなら、真実を口にすべきなのに、人間はそうしていない』本文より
家の本棚には「航路」も「ブラックアウト」も「犬は勘定にいれません」もあるのに(あれ、あるはずのオール…
![]()





「印刷した本は保管するスペースもいるし、時間が経つと保管していた在庫の数も合わなくなります。損傷すれば、売れなくもなります。」本文より
アメリカン・ブックジャムという洋書紹介雑誌の編集者だった著者が、ニューヨークの小出版社ORブックスの…
![]()





「チャップマンの著作が示唆するバナナをめぐるグローバル・ヒストリカルな問題意識は、コーヒーや砂糖などその他の作物について考察するうえでも大いに役立つだろう」解説より
最近の新書ほどではないものの、邦訳タイトルがミスリード気味な、バナナそのものについての歴史ではなく、…




「そうやって息をするやり方を教えてくれ。手をさっと振り、荒波をガラスに変えてしまうやり方を」『マケドニア』本文より
ブルガリア出身のミロスラフ・ペンコフによる、2011年発表のデビュー短篇集。著者は21歳でアメリカに…





「でも、本物だって何人かはいるかもしれない。賞をもらう資格がない人ばかりとは言い切れないんじゃない?」『夜想曲』より
日本生まれのノーベル賞作家ということもあり、日本で最も有名なイギリス現代作家のひとりであろうカズオ・…