ネコ学入門: 猫言語・幼猫体験・尿スプレー




猫はささやく。よりうまく猫に接するためには、猫についての正しい知識が必要だ、と思う。
とうとう我が家にもネコがやってきた。あーかわいい。水槽やケージで飼えない生物を飼うのは初めてなので、…

本が好き! 1級
書評数:201 件
得票数:1212 票
こんにちは。最近は、エネルギー関係の知識をかき集めたり、レヴィ・ストロースの高い視点を模倣してみたり、イザベラ・バードの無垢なまなざしに感動してみたり、そういう読書をしようかな、と思っています。




猫はささやく。よりうまく猫に接するためには、猫についての正しい知識が必要だ、と思う。
とうとう我が家にもネコがやってきた。あーかわいい。水槽やケージで飼えない生物を飼うのは初めてなので、…






人間の希望が時間によって色褪せていって、どうしようもなく摩耗していってしまう物語。
「タタール人の砂漠」を読み終わる。スゴ本さんのブログで見てから、ずっと読みたいなーと思っていて、温め…






日本の社会は、自己言及が機能しないことの代償を、焦土になることで支払っているのだろうか?
半藤一利さんの昭和史(戦前編と戦後編)読み終わった。評判通りオモシロイし、サクサク読めた。毎晩お風呂…






柳田國男は、壮大なロマンチスト、そして強大な文学の磁場であった。しかし同時に、骨の髄まで実践的な人間でもあったのだ。
ずっと僕は、柳田國男のことを「ラスボス」呼ばわりしてきたけども、やっぱり、柳田國男はラスボスだった。…




あのレヴィ=ストロースがトーテミズム論を一刀両断!
読もう、読もうと思っているレヴィ・ストロースの『野生の思考』。つまみ食い的に前のほうを読んでみると、…





政策決定者として、エネルギー問題位どう取り組むか? 日本の報道のみだと抜け落ちがちな、気候変動とエネルギー問題の関係、シェールオイルがエネルギー問題をどう変えたか、などアメリカよりの視点を補充できる。
「エネルギー問題入門」というタイトルではあるが、読み進めると、テーマとしては「アメリカのエネルギー問…




森博嗣Xシリーズ5作目。小川さんが一人になったときに、急に内面の脆いところが露わになる空気が大変好きなんですよ。
大方の予想通り、なにも起こりませんでした(四季が出てくる、とか)。あ、ネタバレ注意です(遅い)。 …





どうやって今の我々があるのか?を忘れないために。我々がどこへ往くのかは知らなくとも、どこから来たのかは知っていなければならない。
「密林の語り部」が先で良かった。彼がどこを目指して物語を紡いでいるのかがわからないと、何のための物語…






人間が非対称の非を悟り、人間と動物との間に対称性を回復していく努力を行うときにだけ、世界にはふたたび交通と流動が取り戻されるだろう。中沢新一のカイエ・ソバージュ最終巻。
ついにカイエ・ソバージュ最終巻まで辿り着いた。1~4巻まで読んできた身としては、こんなにわかりやすい…





スピリットからカミへ、そして唯一神。人間は、どうやって「神」を発明してきたのか。
中沢新一のカイエ・ソバージュ4巻目。「熊から王へ」で、王がどのように誕生してきたのかを明らかにするよ…





コミュニティの再構築、という一番大切なところを物語る。東日本大震災後に書かれた一冊で、明確に震災のこと、震災に大きく人生を狂わされた人々、その後の人々のこと、が描かれている。
久しぶりの池澤夏樹。東日本大震災後に書かれた一冊で、明確に震災のこと、震災に大きく人生を狂わされた人…





ある種の破滅願望から、実際の破滅までの距離。そして、近づいていく加速度。
ついにXシリーズもノベルスで読むようになってしまったことよ。本作は、森博嗣にしては珍しく、動機に踏み…






笹まくら。笹を枕にしたときのように、かさかさと不安な旅。これを「戦争ものだ」というだけで評価するのはもったいない。
■時代の空気を読む この時代、70年代くらいの小説は、いつも不思議な感じがする。「風の歌を聴け」と…






煙に巻くように、無数の物語を編み続けるマルケスと、あくまでも実直に物事を捉えようとするリョサ。2人の対談では、その違いが浮き彫りになる。
マルケスが亡くなったあと、急いで読んだ一冊。ラテンアメリカ文学の巨匠、マルケスとリョサ。2人は対照的…






日々食べる物が変わる、着る服が変わる、生活の仕方が変わる。そうした変化と同じくらい、あるいはもっと根深い変化として、共有する言語や物語が破壊される、ということ。
自分の思想によく連なる内容でありながら、新しい視座を与えてくれる物語だった。 マルケスの「エレ…






犬たちはどうやって自力で伊勢まで辿りつくのか?
■伊勢参りへ プロジェクトの切れ目を狙い、お伊勢参り。日本人の旅行の起源はお伊勢参りにあるという。…





岡本太郎は「石は無口だ」と言った。「岡本太郎の宇宙」最終巻。
ついに辿り着いた。「岡本太郎の宇宙」最終巻。岡本太郎が文化人類学的な観点から世界に向き合っていたとき…




「時計仕掛け」=「四季にコントロールされている」。
以下大変にネタバレというか、既読の人しか意味がわからない考察をします。主に言葉遊びをします笑 …





柳田國男が見つけた「われわれ日本人はどこから来たのか?」の答え方。
ついに遠野物語を読んだ。河童に天狗、こんな世界があるのかって感じで心地よい。でも、これって、なにが凄…




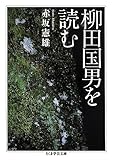
柳田國男の「民俗学」には、柳田その人のきわめて個人的な欲望や無意識の資質といったものが、あまりにも色濃く貼りついている。
岡本太郎が求めた民族学や南方熊楠の民俗学を辿ってきて、やはり、どこにでもその影を落とす柳田國男。日本…