燈火 (銀河叢書)






「どこの家庭も歳月の流れに洗われている。馬淵家とて例外ではない。好きなことは大概たやすく実現できた我が家の黄金期も、いつの間にか遠く流れ去ってしまったわけだと彼は思ったが、(略)」(185頁、7章 幻)
作家自身の家庭をモデルにした小説『素顔』の続編があると知り、さっそく手にしたのが本書です。前作が主…

本が好き! 1級
書評数:732 件
得票数:8728 票
学生時代は書評誌に関わってました。今世紀に入り、当初はBK1(現在honto)、その後、TRCブックポータルでレビューを掲載してました。同サイト閉鎖から、こちらに投稿するようになりました。
ニックネームは書評用のものでずっと使ってます。
サイトの高・多機能ぶりに対応できておらず、書き・読み程度ですが、私の文章がきっかけとなって、本そのものを手にとってもらえれば、うれしいという気持ちは変わりません。 特定分野に偏らないよう、できるだけ多様な書を少しずつでも紹介していければと考えています。
プロフィール画像は大昔にバイト先で書いてもらったものです。






「どこの家庭も歳月の流れに洗われている。馬淵家とて例外ではない。好きなことは大概たやすく実現できた我が家の黄金期も、いつの間にか遠く流れ去ってしまったわけだと彼は思ったが、(略)」(185頁、7章 幻)
作家自身の家庭をモデルにした小説『素顔』の続編があると知り、さっそく手にしたのが本書です。前作が主…




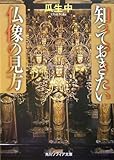
「最大の原動力となったのは人々の釈迦に会いたい、つまり礼拝の対象が欲しいという思いであると考えてよいだろう。」(21頁)
本書のタイトルや「光背とは何か」といった文言がならぶ目次を見て仏像理解のハウツー本と感じ、「ちょっ…





「3・11」で正念場を迎えてしまった科学コミュニケーション
本書の刊行日は2011年2月15日。著者も出版社も、刊行後すぐに科学コミュニケーションの「正念場」…





『不平等社会日本』問題の解答と解説
2000年の日本社会の論壇や読書界から研究者まで、ひとしきり話題をまいた本に同じ著者の『不平等社会…






「もう時間がない。不在の詩人の記憶を掘り起こすより先に、・・・(後略)」(「五右衛門の火」174頁)
なんとも幻惑させられる1冊です。 単行本版の装幀の表紙には、黒を使いません。上半分は薄い緑に、…






「プーさんの周囲はいつも華やいでいて、プーさんは多くの幸せと冨を生み出しましたが、その陰には数々の反目や確執がありました。・・・」
(上の続き) そうしたぬいぐるみのプーさんについての本当の歴史はまだきちんと語られたことがありません…




「科学者になる/である」ことの難しさと面倒くささ
これまでに多くの日本人ノーベル賞受賞者も生まれ、「科学者」に世間的な注目が集まることも少なくない。…





生真面目なアメリカ人か、もしくは、いい加減な日本人か。
科学啓蒙書では著名なガードナーによる、擬似科学や迷信などに対する批判書。ガードナーについては私が紹…






《この列車は、ひとつひとつの駅でひろわれるのを待っている「時間」を、いわば集金人のようにひとつひとつ集めながら走っているのだ。(後略)(116頁)
「最後の作品集」というふれこみで刊行された作者のエッセイ集です。逝去後、数年経っているばかりではな…





想像力を刺激する「何もなさ」
出版不況にもかかわらず、城関連企画の書籍・シリーズは切れ目なく刊行されている。それだけ裾野の広いフ…






「考えてみれば、わたしの幼いころにも明治の面影に触れるよすがはまだいくらかはあったように思います。」(あとがき、236頁)
本書のイラストと文章の両方を担ったのは、同じ出版社から刊行されていたシリーズ「日本人はどのように建…






武士の源流と原像をさぐる日本史学の試み
単行本シリーズ刊行開始時には、旧石器捏造事件の余波で「第1巻」が大幅書き換えになり話題となった。そ…






「やはり正真正銘の極道者だった時代があるのだろうか、(後略)」(本書冒頭)
再読というのは、恐ろしくも興味深いものです。最初に読んだときは自分が「なんとなく」読んでしまったこ…






「戦争が終わったら自由にマンガが書けるようになるだろうね。ぼくはマンガ家になるよ!」(21頁)
2025年度前期の朝ドラ「あんぱん」で、やなせたかしの人生が注目を浴びるにつれ、ドラマにも出てきた…






「夜の散歩も、ほどほどにしなせ」(母ウメから三郎へ、「白木蓮」237頁)
作家自身とその家族をモデルとした小説です。語り手は馬淵三郎という40代半ばの小説家で、妻と娘が3人…





「僕はね、悩みがあるときはよく木に聞いてもらうんですよ。人間よりずっと視野が広いから、木の意見っていうのはかなり参考になります。」(深森護、11頁)
作者にとっての「日常の謎」派ミステリー作家としての単行本デビュー作です。ただし、ミステリー色は濃く…






社会を語り出した脳・神経科学
『サブリミナル・マインド』『〈意識〉とは何だろうか』という一般向けの新書で、鮮やかな解説を見せた著…





「大科学部」創部の理想に向かって
アニメ化もされた『瑠璃の宝石』の作者のデビュー作だそうです。「大科学」という響きに惹かれて、つい手…






ヒトとその先へ、という論点が興味深い1冊
「ヒトの科学」というシリーズ名を見て、興味を惹かれていくつか手にとってみた。 「人間」は、本来…






「問題な漢字」から、「生きている漢字」へ
「読めても書けない漢字」が増えてきたともいわれるが、日本語における漢字の役割は依然大きい。漢字の廃…