ドイツ人が語る ドイツ現代史
![]()




「ドイツ現代史」ではなく、「ドイツ連邦共和国史」そのもの。読者は選ぶが、興味ある人にとってはかなり有益な情報が満載。
本書は邦題が『ドイツ現代史』となっているが、原題は『ドイツ連邦共和国の歴史』である。まさにその通り、…

本が好き! 1級
書評数:73 件
得票数:766 票
基本的には映画好き。
最近小説はめっきり読まなくなり,主に歴史の本ばかり読んでます。
![]()




「ドイツ現代史」ではなく、「ドイツ連邦共和国史」そのもの。読者は選ぶが、興味ある人にとってはかなり有益な情報が満載。
本書は邦題が『ドイツ現代史』となっているが、原題は『ドイツ連邦共和国の歴史』である。まさにその通り、…
![]()





「心理的安全性」というキーワードが気になる人全てにおすすめします。ビジネス書ですが、家族や職場を見直すよい視点が得られます。
「心理的安全性」とは、「みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化」のことを指…
![]()





これはまさに業としかいいようのない、修行の道なのでしょう。よくもまぁ、これだけの「駄作」「珍作」と呼ばれる映画を観られていると思います。
柳下毅一郎さんの映画本は、これまでも何冊か読んできていますが、いつも思うのは、これだけの映画を飽きも…
![]()




「ビッグデータ」とは何か。ほんの少しだけ知識はあっても、それが一体何なのか今一つ全体像を描けない人向けの入門書。何となく大学一年生向けの教科書、といった感じの本です。
「ビッグデータ」なる言葉については、特に東日本震災以降の防災面での活用や、Amazonの「あなたへの…






2020年初頭の現在、世界を席巻している感染症に対する「対処」ではなく、これを「歴史的文脈でとらえる」方法として、本書を読んでみるのはどうでしょうか?
まさに本は「積読」ものである。 以前、『銃・病原菌・鉄』に影響を受け、たまたま古本屋で手にした本書…
![]()




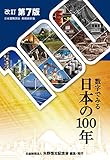
日本国勢図会などに掲載されている資料を、長期的に掲載してある統計資料集。 現代史の記述や、年表とは違った切り口で、明治〜現代、戦後〜現代をみることができます。
このような出版物は、「本」というカテゴリーで書評を書くのは難しい。いわゆる読み物ではないからだ。 本…




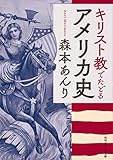
アメリカこそが、世界最大のキリスト教国である、ということを丁寧に解説してくれる一冊。知識ゼロからでは少し難しいけれど、アメリカ史とキリスト教について興味があれば、必読の書。
この本は、『反知性主義』で知られる森本あんりによる、アメリカ合衆国のキリスト教史とでも言うべきもので…
![]()





三味線・琵琶・箏 これらの一つにでも興味があり、どんなルーツをもっているのかが気になる人であれば、是非手にとってもらいたい本。
本書は、いわゆる伝統邦楽の楽器について、筆者なりの観点から、そのルーツ・歴史や、世界の楽器との比較、…






アホウドリから、日本の近代化の光と影が見えてくる。なかなか読んだことのない話が次から次へと出てきます。
本書は、明治以降の日本人が、どのように南洋に進出していったのかについて、アホウドリを中心軸として紐解…
![]()






「専門家」による「ブラタモリ論」としては一つの到達点では。内容・執筆陣がすばらしく、雑誌のままではもったいない。今のうちに単行本化しては?
以前より「地理」では、ブラタモリに言及した記事がちらほらあったように思うが、今回は大々的に「ブラタモ…






まさに先日「三俣山荘」で鹿肉のシチューをいただき、黒部川源流の水を汲み、三俣蓮華岳に登頂したので、全く他人事とは思えない内容でした。
先日はじめて本格的な登山に連れていってもらい、重い荷物を背負いながら、黒部五郎や三俣蓮華岳に登ってき…
![]()




少し思っていたのとは違っていました。「読解力」というよりも、小学生向けの「マッピング」の本ですね。
最近、「読解力」が話題になっているのでそういった本かなと思っていたら、どちらかというと、「マッピング…
![]()






思っていた以上に、日本漫画のカタログ・データベース的な本でした。 漫画史研究のお供に最高です。
尾形光琳の戯画や、渡辺崋山の『一掃百態』など、一つ一つを取り上げても話題が広がるような「戯画本」「漫…






歴史の転換点として、「1905年」は確かに重要だが、ここまでイスラーム押しだとは思わなかった。
山川出版のかなり意欲的なシリーズである、「歴史の転換点」の1冊。 1905年というのは、日露戦争終…
![]()






多分、「ブラタモリ」が好きな人であれば、手に取る価値があると思います。 うまくハマれば、地域研究・フィールドワークの面白さに気づけるかもしれません。
地理学のフィールドワークでは、どんなことをやっているのか、一般の読者にもわかりやすいオムニバスのよう…
![]()





<十字軍国家の憂い> 第一回十字軍成功後、イェルサレムを征服した主力は故郷に帰り、周囲を敵対勢力に囲まれた中での十字軍国家のもがきと苦しみ。 反撃を目論むイスラーム勢力の一枚岩になれない状況。
塩野七生といえば、高校生の頃『コンスタンティノープルの陥落』を読み、かつてこんなに興味深い戦いがあっ…
![]()




いかにして、アメリカは中米のバナナ生産を牛耳ったのか、についての膨大な資料集。 訳文の読みにくさがどうしてもマイナスポイント。 でも、解説が充実しているので、それだけでもおすすめ。
大前提として、この書籍は、著者が膨大な資料にもとづいて、かなりの時間をかけてまとめあげたことであるこ…
![]()




1980年代のちょっと懐かしいアメリカの雰囲気を味わえる名推理短編集。
幸運にも3、4続けて献本していただきました。ありがとうございます。 さて、このシリーズは、〈黒後家…






観た記憶はあるのだけれど、どんだ話だったのか思い出せない映画、映画を観ていながら筋が全くわからない映画、結局何を言いたいのかわからない映画、そしてそもそも観る機会のなさそうな映画、そんな映画の特集本。
「謎の映画」、まさに僕の好きな映画を思い返せば、謎だらけだ。 昭和の時代、深夜のテレビでやっていた…
![]()





「ディナーのあとで 謎解きを」 アイザック・アシモフの名作短編推理小説集。 SF界の巨匠でありながら、こういった軽妙な短編推理小説集を書けるのだから、本当に天才だと思います。
最近の創元推理文庫のリバイバルシリーズのラインナップは、とても魅力的だ。映画分野での同じような企画に…