ぼくたち、Hを勉強しています



男くささを放棄する男、女くささを教科する女
ぎょっとする題名の本だが、中身は案外まともな「性談」。断じて「猥談」ではない、とはじめに宣言されてい…

本が好き! 2級
書評数:23 件
得票数:195 票
自己紹介文がまだありません。



男くささを放棄する男、女くささを教科する女
ぎょっとする題名の本だが、中身は案外まともな「性談」。断じて「猥談」ではない、とはじめに宣言されてい…

世界文学をめぐる旅の記録
柴田元幸と沼野充義。今さら説明の必要もない文学者であるお二人が、2000年から2003年にかけて交互…



「融通無碍の多神教」としての神道
まずはあとがきから引用する。 「私は、かねてから戦後最大のドグマとされる「神道は太古の昔から連綿と…






ひたすらに面白い。面白いとはこういうことだ。
とにかく読んで楽しい。面白いの一言に尽きる。突飛な設定と展開速度の速さ。痛快な切れ味の短編集だ。これ…






「主体」も「歴史」もない。あるのは「構造」のみ。
構造主義。聞いたことはあるが、その内容はさっぱり分からない。なんだか難しそうなイメージばかり先行して…






人間は「物語る動物」である
物語論(ナラトロジー)というものがあるらしい。不勉強なもので、恥ずかしながら本書で初めて知った。スト…

「先生、こんな質問をさせて、どんな意味があるの?」 「それは、君がどんな意味のある人間かによる」
学生に質問をさせて、先生が答える。たったそれだけの本。 だがそれがとてもおもしろい。答える森博嗣の…





めくるめく悪夢のスペクタクル
めっぽう面白い。この本はとにかくその面白さに身をゆだねればいいと思う。あまり深く考えなくともただ読み…






異国のような懐かしき母国
昭和30年代頃からの日本各地の写真集。副題通りに日々の暮らしを主に収めている。 たかだか60年ほど…




主流、大勢、覇権、メインストリーム
労作である。 映画や音楽、舞台など日本語では適当にエンタメと総称される分野は今や世界中に存在し、毎…




植民地支配とは具体的にどういうことか フランスのカンボジア支配を例に 美術史からの観点
19世紀初頭頃から西洋の列強国は次々と現在の東南アジア地域を植民地支配していった。オランダはインドネ…




「おめえ、ヘソねえじゃねえか」
今や「京都ぎらい」がベストセラーとなった著者だが、もともと独特な視点と読みやすい文章で軽妙に日本文化…





ヒトから見たカミ。ヒトにとってのカミ
日本の神々について簡潔にまとめた書。とはいえ民俗学者である筆者が本書でとりあげるのは記紀に記されてい…





日本人の原像を探し続けた民俗学者の記録
日本人は古来から神(カミ)祖霊(タマ)妖怪(モノ)を区別しなかった。すべては等しく畏敬の対象であった…





「人間の安全保障」というあまり聞きなれない言葉の紹介が主題。
異文化への理解が現実に役に立つと具体的に例示している点が面白い。応用人類学という分野だろうか。作者は…






アフリカほど遠い国々もない。そう思っていたが、「アフリカ」とひとまとめにすることがそもそも横暴だと反省した。
名著。作者はジャーナリズムの世界では知らぬ者はいない巨人だという。その作者がアフリカの現状を取材した…




ド直球な推理小説。題名どおり体育館での殺人事件を解き明かすだけの小説だが、論理を考える面白さが純粋にたのしい。



民俗学の初期を記述した歴史書
民俗学の成り立ちをまとめた民俗学学史。著者の判断では南方熊楠は民俗学の成立には関わっていないとして本…



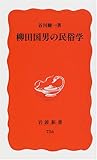
柳田國男を論じることは民俗学者の通過儀礼のようなもの。
民俗学の創始者である柳田國男の膨大な数の作品から、いくつかの主要なものを手際よくまとめた書。さすがに…





網野史観炸裂。上野千鶴子が中立に見えてくるほどだ
網野善彦、宮田登、上野千鶴子の3人が天皇について真っ向から語った対談本。日本を語るなら天皇は避けて通…