単行本の方は2014年12月刊行のおいしい文藝第4弾
「ぐつぐつ、お鍋」です。
内容は(話の順番が違うだけで)同じなので、文庫で十分楽しめます。しかも文庫版には色々な書店の店主さんによる解説があって、本書では「北書店」店主・佐藤雄一氏「暮らしの数だけ鍋がある」を読めて、とってもお得!
「お鍋」=切った具材を鍋で煮込む料理・・・なわけですが、入れる具材・鍋汁・煮込み方に食べ方、食す場所や人数で全然違う料理になってきます。本書で37人の文筆家が語る鍋も、「寄せ鍋」「おでん」「湯豆腐」「すき焼き」など同じものがあっても、内容が全く違うのが面白いところ。
☆ お鍋=しみじみ幸せなイメージなら、ねじめ正一氏「すき焼き 父と二人だけの鍋」。
子供の頃のすき焼きは、「肉が旨くなるんだ」と父が大枚はたいて買った南部鉄の鍋を使ったが、子供たちが必死に肉を食べているのを嬉しそうにみる父はいつも、最後まで肉に手を付けなかった。
それから数年後、27歳の正一青年は糖尿病で体調を崩した父と二人で民芸食器仕入れのため、会津に一泊二日の旅に。宿泊した旅館はオンボロだが、夕飯のすき焼きは会津牛で旨い!・・・のに、出された器は安物で台無し。父発案で仕入れたばかりの器を車まで取りに戻った正一青年、きれいに洗った器を手渡すと「いいなぁ」と父はにっこり笑った。
確かに美しい器はすき焼きにぴったりで、一気に料理が豪華で美味しそうに見え、父と2人で肉も追加して腹いっぱい食べた。その翌年、父は倒れて商売から退き、これが最後の旅行になった・・・。
見守ってきた子供が、一緒に仕事をするくらい大きくなって、同じ審美眼で楽しみながらすき焼きを食べる父が楽しそう。交わす言葉は少なくても、父と息子の心通じる様子がしみじみと優しい話です。
☆ お鍋でも淋しく悲しいこともある・・・と語るのは、筒井ともみ氏「寄せ鍋嫌い」
幼いともみ少女と母、伯父と伯母の4人で形成された家族は、一家団欒・・・からは程遠いギスギス感。精神を深く病んだ伯母、酒を飲みまくる伯父、石のように無口な母と囲む鍋の重苦しさたるや・・・。バラバラ家族に焦燥感を覚えたともみ少女は、小さな手で菜箸を握り、煮え頃の具を選り分けては皆の皿に盛って配り続けた。なんとか家族を取り持つため気を使いするぎる幼女は、気を使いすぎるばかりの寄せ鍋がキライに。
伯父伯母がいなくなった後、母お手製の豪華な寄せ鍋を二人で相対して食すのも苦痛で、シンプルな小鍋を作ってもらってやっとホッとした。
その母も亡くなって、今は一人でシンプル鍋を作ってるけど、いまだに寄せ鍋は苦手。
一家団欒という幻のような匂いの湯気を浴びるだけですっかりくたびれてしまう。
一般的には冬に幸せイメージの鍋が、これほど重苦しくて寂しいことがあるなんて…。
その他、粋な「小鍋だて」と言えば池波正太郎先生、美しく春の月夜に楽しいお鍋は川上弘美氏の「春のおでん」、安野モヨコ氏の「鍋」では
あまりにも独創的過ぎる自分用たれ作りで、恐怖に陥った周囲の人の頭を上げさせない鍋奉行が出現します(笑)。
興味深い鍋料理がいっぱいです!これから寒くなりますから、すべての美味しいもの好きの方に本書をお勧めいたします。
文庫版おいしい文藝シリーズは、以下の通り。ごく地味に増やしていく予定です。よろしくお付き合いください。
第2弾
「ぱっちり、朝ごはん」
第3弾
「ぷくぷく、お肉」
第5弾 本書
第6弾
「ふうふう、ラーメン」






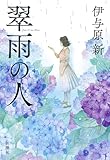


この書評へのコメント