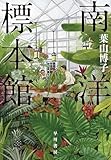千世さん
レビュアー:
▼
人間に愛されて進化してきたネコについて、ネコを愛する著者が徹底的に研究しつくした、かなり専門的な本です。私たちが今ネコの幸せのためと信じて行っていることは、ネコの未来のために正しいことなのでしょうか。
タイトルからして、ネコについてのエッセイみたいなものかと思って軽い気持ちで読み始めたところ、予想に反して、ネコの習性や進化の過程、社会との関わり方、果てはネコの未来についてまで、観察や実験、発掘などの研究を重ねて記した、かなり専門的な「猫学」とでも言うべき本でした。
ネコを愛する著者が、ネコという動物を徹底的に研究し、その全てを語り尽くした本なので、新たな発見や驚くことは多々ありましたが、私が一番興味を持ったのは「ネコの歴史」についてです。そこには、ネコが人間に愛されるが故の迫害の歴史もありました。
どのように野生のヤマネコがイエネコになったのかはまだ謎だということですが、その起源は1万年も前にさかのぼるそうです。そしてイエネコが人間の家で暮らすようになったのは、今から3500年前のエジプトということですから、歴史の古さに驚きます。日本では平安時代の貴族に飼われるようになったと言われているので、エジプトから何千年もかけて人間によって船に乗せられ、海を渡ってきたということですね。
そしてそのエジプトでは、ネコに霊的な意味を与えたがためにネコをミイラ化し、参拝客に売っていたと言います。ミイラ用のネコの繁殖もしていたとか。また17世紀のイギリスでは、ネコを魔女が変身した姿と見て火あぶりにすることもあったそうです。それもこれも人間にとってネコがあまりに魅力的で、神や魔女と目されるほど神秘的に見えたからだと言えるでしょう。私は谷崎潤一郎の『猫と庄造と二人の女』やコレットの『牝猫』など、男がネコをかわいがりすぎて女に嫉妬される小説のことを考えてしまいました。
ネコを語る上で忘れてならないのが、ネコの驚異的な繁殖力です。私たちは今、去勢という方法でそれを乗り越えようとしています。その手段がなかった頃、人間は普通にいらない子ネコを殺していたそうです。また野良ネコたちの社会では、雄が子ネコを殺すそうです。それを思うと、去勢という方法は人間とイエネコが共存していくにあたって、もっとも適切な方法であるように思えます。しかし、この本を読んでいるとそれもわからなくなってきました。
著者は未来のネコについても考察しています。かつてイエネコは、ネズミを駆除する害獣駆除係として人間と共存してきました。今やネコはその役割を終え、完全にペットとして、家族として人間社会に溶け込んでいます。そのために私たちは、ネコをその習性に反して家の中に閉じ込めて守り、去勢をして繁殖能力を失わせ、それが人間にとってもネコにとっても最善の生き方だと信じています。
しかし著者が警鐘を鳴らすのは、この世にいる全てのネコに去勢をすることはできないということです。人間による捕獲の手を免れて生き残ったネコは必ずどこかに存在し、繁殖し続けます。ネコの遺伝についても研究した著者は、人間に簡単につかまるおとなしいネコは去勢されて遺伝子が絶え、人間に慣れない野性的なネコだけが子孫を残してしまう可能性を心配しています。ネコはいつか凶暴に進化し、野生動物たちにとっての脅威となってしまうのでしょうか。
わが家のネコは、生後2か月にも満たない頃にうちへ来て、以来外へ出たことも、他のネコに会ったこともほとんどありません。本著から知るネコのコロニーの様子などを想像すると、イエネコといえどもやはりネコと共に生きるのが本来の姿なのだろうかとも考えます。何が正しいのかわからず、迫害された過去のネコや、未来のネコのことを思うと切なくなってきます。ただひとつだけ確信を持って言えるのは、うちにいるこの子が、「いつ見ても幸せそうに見える」ということです。尻尾をぴんと立てて私たちを玄関まで迎えに来て、あとはそばでお腹を出してぐっすり眠っている姿を見ると、不幸せとは到底思えません。この子を最期の時までそのままの姿で見送ること、それが私たち夫婦の使命です。
ネコを愛する著者が、ネコという動物を徹底的に研究し、その全てを語り尽くした本なので、新たな発見や驚くことは多々ありましたが、私が一番興味を持ったのは「ネコの歴史」についてです。そこには、ネコが人間に愛されるが故の迫害の歴史もありました。
どのように野生のヤマネコがイエネコになったのかはまだ謎だということですが、その起源は1万年も前にさかのぼるそうです。そしてイエネコが人間の家で暮らすようになったのは、今から3500年前のエジプトということですから、歴史の古さに驚きます。日本では平安時代の貴族に飼われるようになったと言われているので、エジプトから何千年もかけて人間によって船に乗せられ、海を渡ってきたということですね。
そしてそのエジプトでは、ネコに霊的な意味を与えたがためにネコをミイラ化し、参拝客に売っていたと言います。ミイラ用のネコの繁殖もしていたとか。また17世紀のイギリスでは、ネコを魔女が変身した姿と見て火あぶりにすることもあったそうです。それもこれも人間にとってネコがあまりに魅力的で、神や魔女と目されるほど神秘的に見えたからだと言えるでしょう。私は谷崎潤一郎の『猫と庄造と二人の女』やコレットの『牝猫』など、男がネコをかわいがりすぎて女に嫉妬される小説のことを考えてしまいました。
ネコを語る上で忘れてならないのが、ネコの驚異的な繁殖力です。私たちは今、去勢という方法でそれを乗り越えようとしています。その手段がなかった頃、人間は普通にいらない子ネコを殺していたそうです。また野良ネコたちの社会では、雄が子ネコを殺すそうです。それを思うと、去勢という方法は人間とイエネコが共存していくにあたって、もっとも適切な方法であるように思えます。しかし、この本を読んでいるとそれもわからなくなってきました。
著者は未来のネコについても考察しています。かつてイエネコは、ネズミを駆除する害獣駆除係として人間と共存してきました。今やネコはその役割を終え、完全にペットとして、家族として人間社会に溶け込んでいます。そのために私たちは、ネコをその習性に反して家の中に閉じ込めて守り、去勢をして繁殖能力を失わせ、それが人間にとってもネコにとっても最善の生き方だと信じています。
しかし著者が警鐘を鳴らすのは、この世にいる全てのネコに去勢をすることはできないということです。人間による捕獲の手を免れて生き残ったネコは必ずどこかに存在し、繁殖し続けます。ネコの遺伝についても研究した著者は、人間に簡単につかまるおとなしいネコは去勢されて遺伝子が絶え、人間に慣れない野性的なネコだけが子孫を残してしまう可能性を心配しています。ネコはいつか凶暴に進化し、野生動物たちにとっての脅威となってしまうのでしょうか。
わが家のネコは、生後2か月にも満たない頃にうちへ来て、以来外へ出たことも、他のネコに会ったこともほとんどありません。本著から知るネコのコロニーの様子などを想像すると、イエネコといえどもやはりネコと共に生きるのが本来の姿なのだろうかとも考えます。何が正しいのかわからず、迫害された過去のネコや、未来のネコのことを思うと切なくなってきます。ただひとつだけ確信を持って言えるのは、うちにいるこの子が、「いつ見ても幸せそうに見える」ということです。尻尾をぴんと立てて私たちを玄関まで迎えに来て、あとはそばでお腹を出してぐっすり眠っている姿を見ると、不幸せとは到底思えません。この子を最期の時までそのままの姿で見送ること、それが私たち夫婦の使命です。
投票する
投票するには、ログインしてください。
国文科出身の介護支援専門員です。
文学を離れて働く今も、読書はライフワークです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:早川書房
- ページ数:0
- ISBN:B00RKN47QI
- 発売日:2014年11月25日
- 価格:970円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。