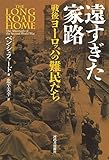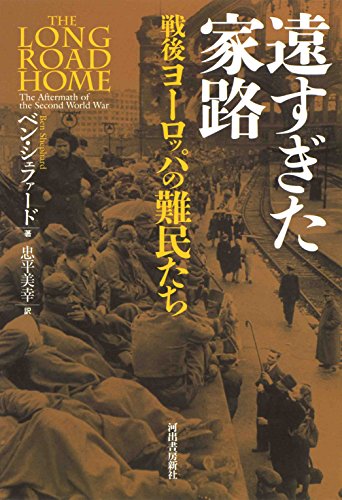ぽんきちさん
レビュアー:
▼
戦いすんで 日が暮れて 我が帰る家は いずこにありや
1945年、第二次世界大戦が終わった。
戦争が終わったのは喜ばしいことだった。しかしながら、人々の暮らしが、直ちに何事もなかったように大戦前に戻るわけではもちろんなかった。
大戦の6年間は、大量の人員移動を生んでいた。強制的に駆り出された外国人労働者。自発的な出稼ぎ労働者。強制収容所に入れられた「罪人」たち。居住地がナチス・ドイツに併合され、故郷を追われた人々。「アーリア人」風の外見を持つがゆえ「ゲルマン化」のために誘拐された子供たち。
そうした人々は、大戦終了とともに、「我が家」に帰るべきであった。
しかし、帰るべき家がなければどうか。政情が変化しすぎて、故郷に戻りたくなければどうしたらよいのか。目指す場所が決まったとして移動手段はあるか。帰り着くまでどうやって食いつないでいけばよいのか。
大規模な戦争の終結は同時に、大量の難民の発生を意味していたのだ。
本書ではこうして生じたヨーロッパの大量の難民たちの処遇を丁寧に丹念に追っている。
難民たちは、DP(=Displaced Person)と呼ばれた。「避難民」「流民」などと訳される言葉だが、ニュアンスとしては「行き場をなくした人々」といった感じだろうか。
こうした人々を助けるべく組織された国際機関がUNRRA=「連合国救済復興機関」である。
DPたちの扱われ方や目指す定住先は、それぞれの出身国や立場によってもいろいろだった。UNRRAは、彼らを支援するため、国を超えて設立された。できるだけDPたちの実情に合わせ、速やかにことを進めるべき立場にあったが、諸般の事情でいつも最適な処置をとれるわけではなかった。ロシア人、ウクライナ人、ユダヤ人、子供たち。さまざまな立場のDPの発生とその行く先を巡るあれこれが、章ごとにまとめられている。
「戦勝国」である、例えばイギリスにもアメリカにもそれぞれの事情があり、だからこそ、国を超えた機関が必要ではあった。だが理念は理念として、UNRRAは必ずしも最適な処置を講じられたわけではなかった。現場にはどうにかしようと努力する多くの善意の個人がいながらも。DPに関わる悲喜劇は、数年間にわたって繰り広げられた。ここに端を発する火種もあり、また、パレスチナ情勢なども考え合わせると、いまだDPの家路を巡る問題は終わっていないとも言える。
大混乱の中で、何が起こりうるのか。先行きが見えない中で、個々人はどう考え、何を選択すべきなのか。
決して遠くない昔に起きた一連の出来事は、現代の難民問題にも通じる教訓を孕んでいるようにも思われる。
労作である。
戦争が終わったのは喜ばしいことだった。しかしながら、人々の暮らしが、直ちに何事もなかったように大戦前に戻るわけではもちろんなかった。
大戦の6年間は、大量の人員移動を生んでいた。強制的に駆り出された外国人労働者。自発的な出稼ぎ労働者。強制収容所に入れられた「罪人」たち。居住地がナチス・ドイツに併合され、故郷を追われた人々。「アーリア人」風の外見を持つがゆえ「ゲルマン化」のために誘拐された子供たち。
そうした人々は、大戦終了とともに、「我が家」に帰るべきであった。
しかし、帰るべき家がなければどうか。政情が変化しすぎて、故郷に戻りたくなければどうしたらよいのか。目指す場所が決まったとして移動手段はあるか。帰り着くまでどうやって食いつないでいけばよいのか。
大規模な戦争の終結は同時に、大量の難民の発生を意味していたのだ。
本書ではこうして生じたヨーロッパの大量の難民たちの処遇を丁寧に丹念に追っている。
難民たちは、DP(=Displaced Person)と呼ばれた。「避難民」「流民」などと訳される言葉だが、ニュアンスとしては「行き場をなくした人々」といった感じだろうか。
こうした人々を助けるべく組織された国際機関がUNRRA=「連合国救済復興機関」である。
DPたちの扱われ方や目指す定住先は、それぞれの出身国や立場によってもいろいろだった。UNRRAは、彼らを支援するため、国を超えて設立された。できるだけDPたちの実情に合わせ、速やかにことを進めるべき立場にあったが、諸般の事情でいつも最適な処置をとれるわけではなかった。ロシア人、ウクライナ人、ユダヤ人、子供たち。さまざまな立場のDPの発生とその行く先を巡るあれこれが、章ごとにまとめられている。
「戦勝国」である、例えばイギリスにもアメリカにもそれぞれの事情があり、だからこそ、国を超えた機関が必要ではあった。だが理念は理念として、UNRRAは必ずしも最適な処置を講じられたわけではなかった。現場にはどうにかしようと努力する多くの善意の個人がいながらも。DPに関わる悲喜劇は、数年間にわたって繰り広げられた。ここに端を発する火種もあり、また、パレスチナ情勢なども考え合わせると、いまだDPの家路を巡る問題は終わっていないとも言える。
大混乱の中で、何が起こりうるのか。先行きが見えない中で、個々人はどう考え、何を選択すべきなのか。
決して遠くない昔に起きた一連の出来事は、現代の難民問題にも通じる教訓を孕んでいるようにも思われる。
労作である。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:河出書房新社
- ページ数:625
- ISBN:9784309226262
- 発売日:2015年03月20日
- 価格:5076円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。